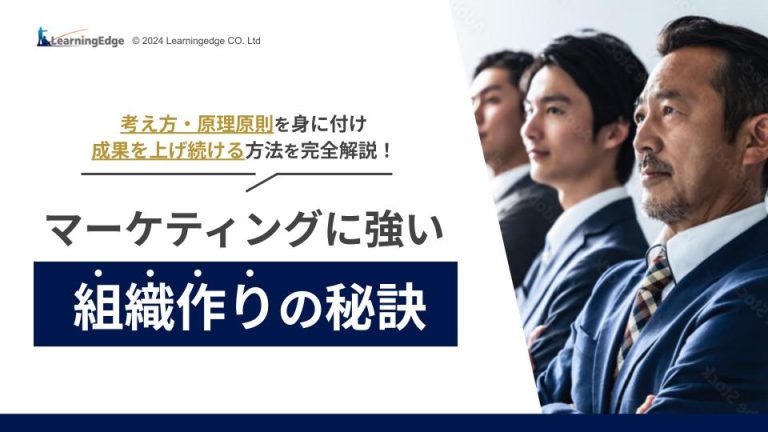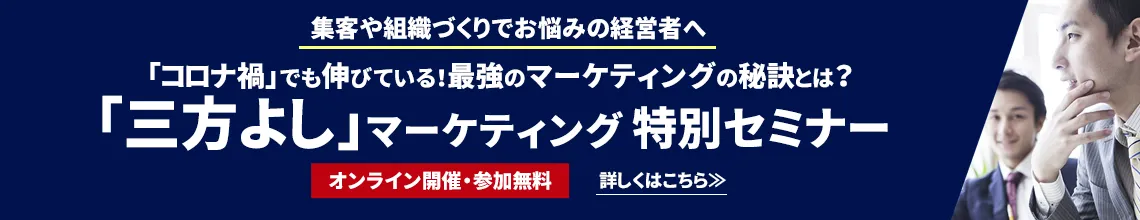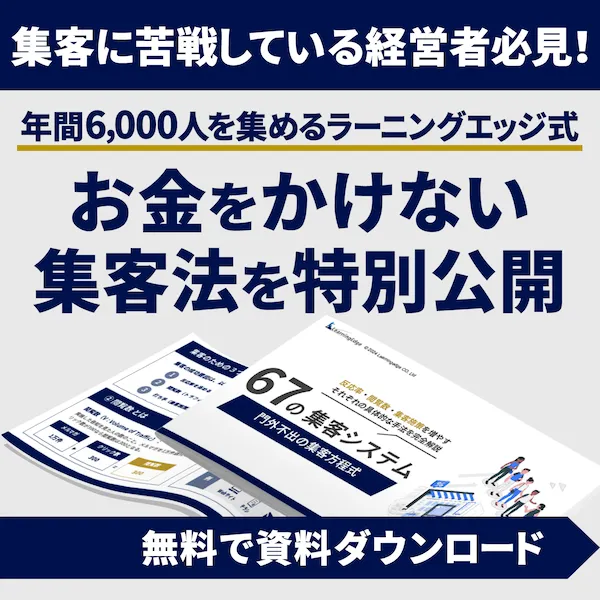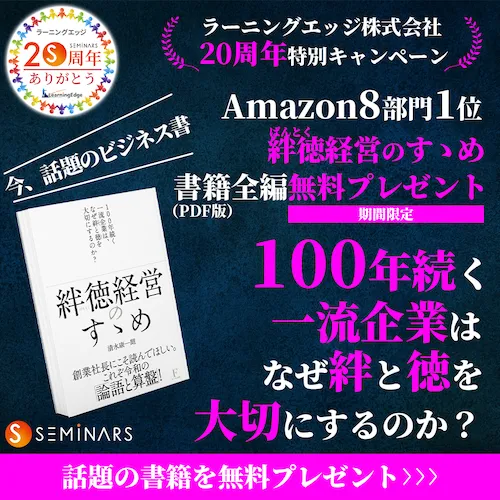アドラー心理学とは、心理学の世界三大巨匠の一人であるアルフレッド・アドラー(Alfred Adler)が提唱した理論です。
「勇気の心理学」とも呼ばれ、自己成長や人間関係の改善に役立つ考え方が特徴です。
近年では、「嫌われる勇気」などのベストセラーによって注目され、多くの人が人生や仕事に取り入れています。
本記事では、アドラー心理学の基本的な理論や思想を紹介するとともに、その活用方法やメリット、さらにおすすめの書籍について詳しく解説します。
アドラー心理学とは?

アドラー心理学とは、心理学の世界三大巨匠とも呼ばれるアルフレッド・アドラー(Alfred Adler)が提唱した思想のことです。
個人の悩みは、過去に起因するのではなく、未来をどうしたいという目的に起因して行動を選択している。
アドラー心理学では、「〜だから、〇〇になる」という原因論ではなく、人間は目的を果たすために生きていて、自分自身でその道を選択していると言います。
例えば、『幼い頃に親から虐待を受けていたから(原因)、会社のみんなとうまく話すことができない(結果)』という考え方を指します。
「過去の原因→結果」ではなく、『会社に入社して他者と関係を築きたくないため(目的)、幼い頃の虐待された記憶を持ち出している(自身で選択)』という心理です。
「目的を果たすために自分自身でその道を選択している」と考えるのがアドラー心理学の代表的な思想です。
なぜ今人気になったのか?
2013年に岸見一郎氏と古賀史健氏による、アドラー心理学を元に執筆された共著「嫌われる勇気」が世界中で大ヒットしました。
日本国内でも200万部を超えるメガヒットとなり、テレビやYouTubeなどで連日取り上げられるほどでした。
今でこそ、心理学に興味のある人からすると知らない人はいないほど有名になった“アドラー”ですが、従来は3大心理学者(フロイト、ユング)の中では知名度が1番低いと言われていました。
現代はインターネット・SNSが発達したことにより他者との比較が加速し「自分らしさとは何か?」を疑問に感じ、「アドラー心理学ではどう解釈するか?」と考える人が増えはじめています。
アドラー心理学は人間とうまく付き合っていく方法、また自分と真っ直ぐ向き合う方法を教えてくれる心理学として、今なお人気を博しています。
アドラー心理学の5つの理論

ここからは、アドラー心理学の5つの理論について解説していきます。
認知論
アドラー心理学の5つの理論1つ目は、「認知論」です。
認知論とは、現実は目の前のものを見ているのではなく、その現実を自ら意味づけて解釈したものを体験している考え方のことを指します。
アドラー心理学的解釈では、人は事実そのものを体験しているのではなく、事実の“解釈”を体験していると言われています。
経営者的視点で俯瞰しても、経営者とスタッフでは一つの数値的結果を見ても、受け取る意味合いは違うでしょう。
つまり、人生は「起きたことをどのように解釈するか」で大きく体験や現実を変えることができるのです。
認知論(例)|水の入ったコップがある場合

画像のコップを見て、どのように意味付けしますか?
- 「水が半分も入っている」
- 「水が半分なくなっている」
このように、同じコップ(同じ現実)を見えているにも関わらず人によって解釈の仕方が変わります。
つまり『解釈の仕方で人生(現実)を変えてしまう』ということだと、アドラーは言います。
アドラー心理学によると、私たち人間は現実そのものを体験しているのでありません。物事をどのように意味付けし、その意味づけしたものを体験しているにすぎないのです。
目的論
アドラー心理学の理論2つ目は「目的論」です。
目的論とは、人間は目的を果たすために、行動をしているという考え方のことを指します。
アドラーは「自分が置かれている環境は、自分の目的を達成するために自分自身で選択した結果である」と言います。
目的論(例)|子どもが寝る前に電気を消すと泣く場合
寝る前に電気を消すと子どもが泣いてしまう場合があります。
「暗闇が怖い(原因)から泣いている(結果)」と思う方は多いのではないでしょうか?
しかし、アドラー心理学の目的論で解釈してみると次のようになります。
「母親の関心を引くために(目的)、暗闇を使い“怖い”という感情を作り出している」
このように『目的を果たすために行動している』という考え方がアドラー心理学の目的論です。
解釈の仕方で受け止め方が全く変わります。
全体論
アドラー心理学の理論3つ目は「全体論」です。
全体論とは、人間は精神、意識や無意識、また肉体すべてにおいて『分割できない存在』という思考法です。
しかしながら、実際には「意識」「無意識」「精神」といった、部分的に分割してから人間を考察していく必要があると、アドラー心理学では学びます。
最も重要になるポイントは幅広く分割して考察したとしても、それで人間のすべてが理解できるわけではないということです。
全体論(例)|メンタルを強くしたい場合
例えば、プレゼンで堂々とパフォーマンスするために「メンタルを強くしたい」と思っている場合、どんな要素に焦点を当てて改善したらいいかを考えます。
ここで「心」だけに焦点を当てて改善したとしても、「心」だけの改善では最高のパフォーマンスをするためには限界があるでしょう。
「技(話すスキル)」を改善するために“勉強”して自信をつけたり、「体(体力)」を改善するために“筋トレをする”といった、さまざまなアプローチ方法があるというのがアドラー心理学的考え方です。
このように、他の要素と複雑に相互作用している“統一体”という考え方を、アドラー心理学では「全体論」と言います。
対人関係論

アドラー心理学の5つの理論4つ目は「対人関係論」です。
対人関係論とは、社会の中で個人と個人のつながりは必ずあるため、どんな悩みも必ず他者の影が存在するという考え方のことを指します。
人が生きていくうえで、どんな場面においても「人」と必ず関わっているため、悩みのすべては“対人関係”の悩みであるとアドラー心理学では説かれています。
私たち人間は、「新しい職場で、いい人間関係を構築していきたい」と思っている人ほど、「相手を観察し、相手のためになにができるのか?」と考える傾向があります。
このように、「自分の悩み」は「他者からの影響(すべての行動に相手役がいる)」を受けているからこそ発生するということを、アドラー心理学では学べます。
対人関係論(例)|自身の内面の問題に見える悩みの場合
例えば、下記のように自身の内面の問題に見える悩みでも、すべては他者から影響を受けているとアドラー心理学では学びます。
- 孤独感・虚無感が襲ってくる
- 行動ができない
- 自分にはなにも価値がない
- コンプレックスがある
- 部屋に引きこもりたい気分
自分自身の問題と捉えがちな悩みも、他者と比較していることで引き起っている「劣等感」が根底で影響しているというのが、アドラー心理学的思考です。
自己決定性
アドラー心理学の理論5つ目は「自己決定性」です。
自己決定性とは、自分のすべての行動は自分自身で決めることができるという考え方を指します。
すべての悩みに対人関係があろうとも、それによって勝手に人生が決まるということでなく『自ら行動を決定しているし、決定できる』という個人の独自性、現実の見方に関する理論です。
コントロールできない対人関係の悩みがあっても、「自分を変えたい」と勇気を持って行動すれば「少しずつ悩みから脱却される」といった前向きな人間観です。
この「自己決定性」を元に思考を進めることで、「自分で生き方を選んでこの仕事を選んだ」「お客さまとの関係性を深めるにはどうしたらいいか」など、自らの意思を強めて関係性を進化させることができるようになると、アドラー心理学では言います。
アドラー心理学の思想

ここからは、アドラー心理学で用いられている代表的な思想をピックアップしてご紹介していきます。
劣等感
劣等感とは、自分を他人と比べることで「劣っている」と感じることを指します。
アドラー心理学において、『劣等感』を持つことは悪いことではありません。
劣等感は、理想とする自分を描いているからこそ芽生える感情です。劣等感を利用することで理想の自分に近づくことができるとアドラーはいいます。
例えば、恋愛のパートナーに「稼ぐ力がない(年収が低い)」という理由でフラれた場合は、次のように落ち込むかもしれません。
- 「僕は、稼げないからダメな人間だ...」
- 「年収が◯万円あれば振られなかった」
ここで、アドラーが肯定する「劣等感」を力に変えたとするなら、次のような受け止め方になります。
- 「もっと効率的に稼ぐためにビジネスを学ぼう」
- 「年収を上げるためにマーケティングを学ぼう」
能動的な意欲が湧き、自分が心から実現したいと思っている欲求を教えてくれる重要な感覚になります。
課題の分離
課題の分離とは、自分と相手の課題を分離して考える思想のことです。
アドラーは、自分の課題を解決するために生きる、そして他人の課題に勝手に介入してはならないと説きます。
例えば、「部下に間違いを注意しなければいけない」シーンがあったとします。
- 「なんて注意すれば傷つかないか?」
- 「この言い方では嫌われるのではないか?」
- 「優しく言いすぎると、また同じミスをするかも」
このように、相手がどう思うかを考えてしまうことは誰しもあるものです。
しかしながら、アドラー心理学でいう“課題の分離”に従う場合、すべて「相手の課題」に該当します。
部下が傷ついてしまうかどうか、嫌うかどうか、同じミスをするかどうかなどは、部下自身の課題であるため自分がコントロールすることはできません。
その代わり、部下が気づかないように伝える方法や考え方を伝えることは、「伝える側の責任」となるということは間違いありません。
勇気づけ
勇気とは、自己課題を乗り越えるために必要なエネルギーのことです。
別名「勇気の心理学」と言われたほど、アドラー心理学において『勇気』についての学ぶことは重要なポイントだといえます。
勇気づけは、困難を乗り越える活力を与えること、またその困難に立ち向かうための精神的な能力を身につけることだとアドラー心理学では学びます。
勇気があれば、なんでもできる!
勇気を持てば、事態はよい方向へと進んでいく!
勇気がない人間は、劣等感を理由に行動しなかったり、責任から逃げたりなど、変化・成長を止めてしまいその先の未来に進もうとしません。
「勇気」こそが人生を変えるのです。
共同体感覚
共同体感覚とは、自分は「共同体の一部(周りと繋がっている感覚)」と主観的に感じる思想のこと、また他人へ関心を向けることだとアドラーは言います。
私たちが生きていくためには、「学校」「職場」「家族」といったコミュニティに属して生きている社会的な面があるとアドラーは説きます。
生きていくうえで、共同体感覚を持ちながら他人を尊重し幸せにすることが、自分の幸せにも繋がります。
① 相手を無条件に信頼する
② そのままの自分を受け入れる
③ 他人の役に立つ行いをする
共同体感覚を持つためには、上記の3つの思想が必要です。
無条件に信頼し仲間の役に立つことで自分の価値を感じることができます。ここで、相手の承認欲求を満たせているかどうかは『相手の課題』になります。
誰かのために行動することで共同体感覚が生まれ、課題の分離(自分の課題)も可能で、誰かのため、何かのために行動するという視点はビジネスにおいて欠かせない価値観です。
ぜひ以下の記事もご覧いただき、成果を上げるマーケティング戦略の価値観や心理学についての知識も深めてください。
アドラー心理学を活用するメリット
アドラー心理学を職場で活用すると、個人の成長だけでなく、チーム全体のパフォーマンス向上や人間関係の改善につながります。
ここでは、アドラー心理学を活用する具体的なメリットを解説します。
主体性が高まり自己肯定感が向上する
アドラー心理学の「自己決定性」は、「自分の人生の方向性や行動を自ら選び取る」という意識を育てます。
職場では従業員が他者の指示を待つのではなく、「自分はこの状況でどう動くべきか」と自発的に考えて行動する力を引き出すのです。
例えば、業務で失敗を起こした際にも、「この失敗を次にどう活かすか」と考え、自ら再挑戦する文化を醸成できます。
このような主体性の発揮は、従業員一人ひとりの自己効力感を高め、結果的に組織全体のパフォーマンス向上へとつながります。
モチベーションが持続する
アドラー心理学の「勇気づけ」は、結果だけでなく、過程や努力そのものにも価値を見出す考え方です。
例えば、ある取り組みが結果につながらなかったとしても、リーダーが部下に「この工夫がチームの役に立ったよ」と伝えれば、部下は自分の努力が評価されたと感じます。
このような小さな積み重ねが、短期的な結果に左右されず、長期的なモチベーションを支えるのです。
努力を称賛する文化が職場に根付けば、メンバーが意欲的に行動しやすい環境が生まれます。
的確な判断力を身につけリーダーシップが高まる
アドラー心理学の「課題の分離」は、リーダーが自分の役割に集中し、効率よく意思決定を行うための考え方です。
この考え方を活用すると、例えば部下が顧客対応で困っているとき、その問題が「誰の課題なのか」を冷静に判別することができます。
それが、部下の課題だと分かれば、リーダーは無駄な介入を避けつつ、必要なサポートを的確に行えるのです。
こうしたアプローチを取ることで、リーダーは組織全体をまとめる指揮やビジョンの共有といった本来の役割に集中できます。
その結果、業務がスムーズに進み、チーム全体の信頼感も自然と高まります。
ストレスが減り良好な人間関係が築ける
アドラー心理学の「認知論」は、出来事そのものではなく、「それをどう解釈するか」がストレスの原因になると唱えています。
例えば、同僚と意見が食い違った場合、「考え方が違うのは当然」と受け止めるだけで、対立を避け、新しい視点を得るチャンスに変えられます。
また、リーダーが「あなたの意見をもっと知りたい」と伝えると、相手は自分が尊重されていると感じ、自然と信頼が生まれます。
このように、解釈を変えるだけで、人間関係はストレスの原因から成長を促す場に変わります。
チーム全体で目標を達成しやすくなる
アドラー心理学の「目的論」は、「なぜその行動をするのか」という目的をはっきりさせることで、チームが目標達成に向けて一丸となれるようにする考え方です。
例えば、部下に「この目標を達成することが、個人の成長だけでなく、チーム全体の成功につながるんだ」と伝えてみましょう。それだけで、タスクがただこなすだけの作業ではなく、「やりがいを感じる挑戦」に変わります。
こうした言葉を日々伝えていくと、メンバーが自然と目標の大切さを共有するようになります。そして、一体感を持って行動できる雰囲気が職場に生まれます。結果的に、チーム全体の目標達成力が高まるはずです。
意見交換が活発になり職場に創造性が生まれる
アドラー心理学の「共同体感覚」は、「誰もが対等で必要な存在である」という意識を育む考え方です。
この感覚を職場で大切にすると、リーダーや部下といった立場を超えて自由に意見を交換しやすくなります。
例えば、リーダーが部下の意見に「そんな考え方があるんだね。面白いね」と共感してみましょう。
それだけで、相手は自分のアイデアに自信を持ち、さらに発展させようとします。
こうした関わりを積み重ねることで、職場全体に創造性が広がります。その結果、新しい価値やイノベーションが自然と生まれていきます。
アドラー心理学を学ぶための書籍紹介

アドラー心理学を学ぶための書籍を紹介します。
嫌われる勇気|自己啓発の源流「アドラー」の教え

「嫌われる勇気」は、紹介した「勇気づけ」「課題の分離」などが詳しく解説されている書籍です。
コントロールができない他人の課題に介入せずに、自分の課題を解決するために生きていくことの重要さ“勇気”を教えてくれる大ヒット書籍です。
主人公と先生との対話形式で進んでいくため、とても読みやすい作品です。
幸せになる勇気|自己啓発の源流「アドラー」の教えII
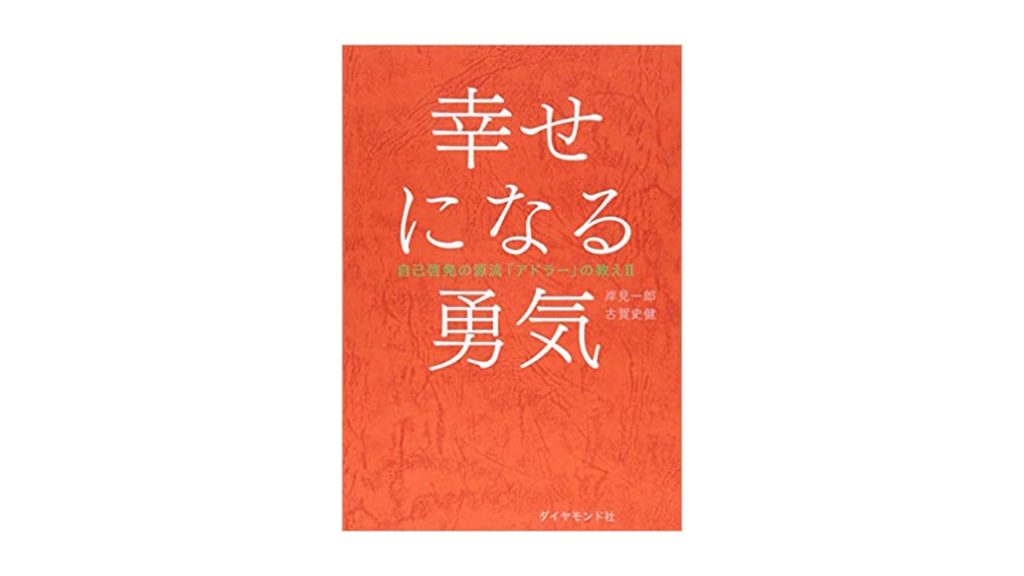
「幸せになる勇気」は、「自立」や「愛」について書かれていて、自分から人を愛する大切さを学ぶことができる書籍です。
自分を愛してくれるかは他人の課題であるため、自分ができることは「人を愛すること」だけだと気付かされます。
嫌われる勇気の続編とも呼ばれていて、人生を一変させる1冊になるでしょう。
コミックでわかるアドラー心理学
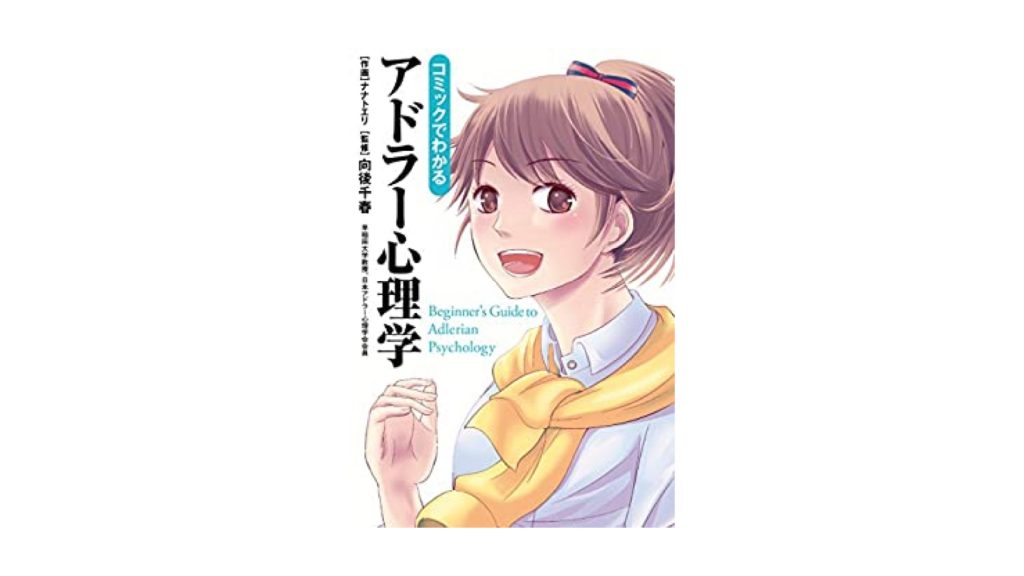
「コミックでわかるアドラー心理学」は、文字ばかりが苦手な方向けで手軽にアドラー心理学のことを知ることができます。
『嫌われる勇気』を読む前に、こちらのマンガを先に読むことで、よりアドラー心理学が学びやすいです。
スッと内容が入ってきやすい作品なので、ぜひご覧ください。
アドラー心理学入門
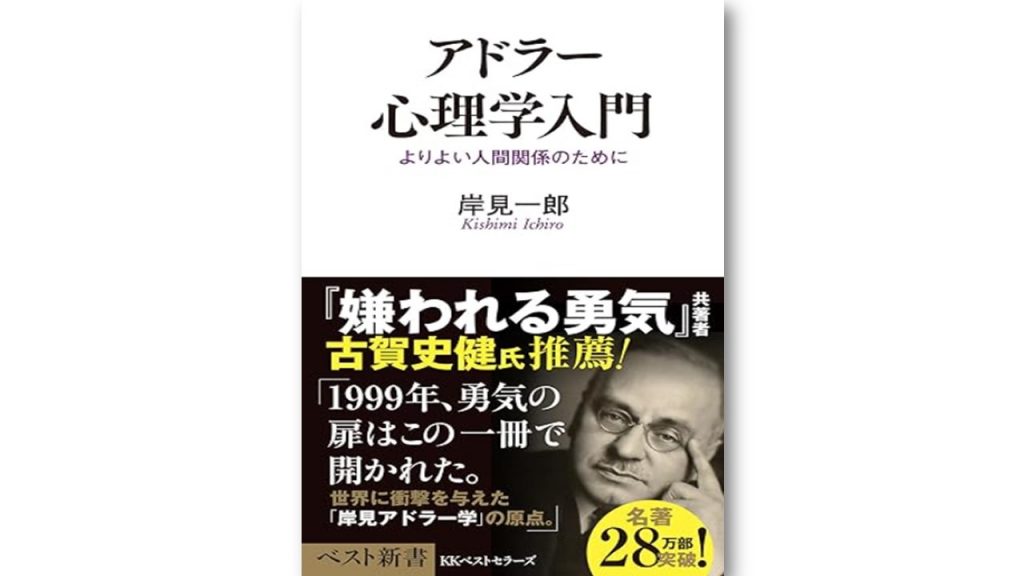
「アドラー心理学入門」は、アドラー心理学を体系的に学びたい方にぴったりの入門書です。著者は岸見一郎氏で、本書では幸福に生きるための考え方や、アドラー心理学の基本的な理論をわかりやすく解説しています。
例えば、「劣等感との向き合い方」や「課題の分離」について、日常生活や仕事にどう活かせるかを具体的に学ぶことができます。
また、「罰しない育児」や「ほめるのではなく勇気づける教育法」といったテーマは、リーダーシップや人材育成のヒントとしても役立つでしょう。
さらに、初心者でも無理なく読み進められるよう構成も工夫されています。専門的な内容を扱いながらも読みやすさに配慮された一冊です。
アドラー心理学|人生を変える思考スイッチの切り替え方
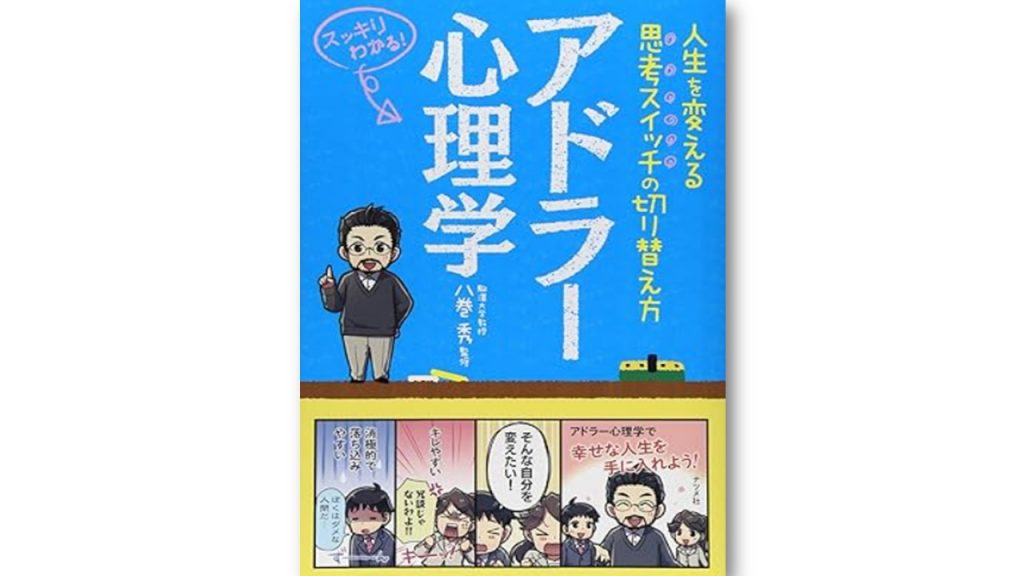
「アドラー心理学―人生を変える思考スイッチの切り替え方」は、「ありのままの自分を受け入れて思考のクセを少し変えるだけで人生は変わる」というメッセージを漫画やイラストを交えて楽しく伝えてくれます。
著者の八巻秀氏は臨床心理士で、心理学に馴染みがない方でも取り組みやすい内容に仕上げています。
また、日常の悩みに対して会話形式で解決策を提案するカウンセリングコーナーもあり、すぐに役立つアドバイスが詰まっています。
気軽に学びながら、自分を変える一歩を踏み出したい方におすすめです。
不安や悩みがすぐに軽くなるアドラー心理学
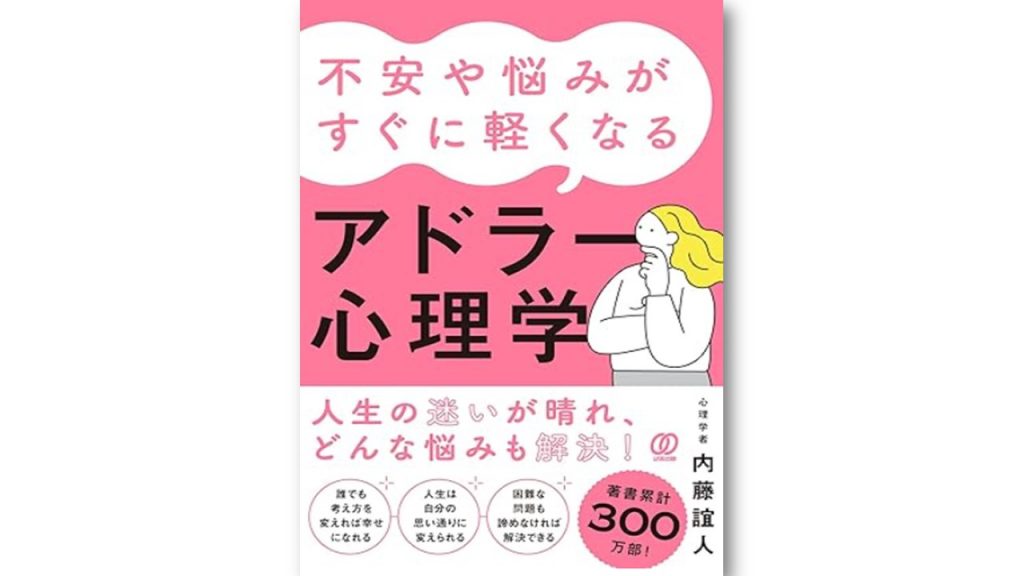
※本の画像を挿入
「不安や悩みがすぐに軽くなるアドラー心理学」は、アドラー心理学と現代心理学の研究を融合した一冊です。
著者の内藤誼人氏は、アドラーの「どんな悩みも自分で解決できる」という基本的な考え方をもとに、人生の迷いやモヤモヤを晴らす具体的な方法を紹介しています。
例えば、劣等感をモチベーションに変える思考法や人間関係を楽にする視点の切り替え方など、日常で役立つテクニックが多く含まれています。
さらに、睡眠や姿勢の改善がメンタルに与える影響など実践的なアプローチも多く、心の負担を軽くして前向きな人生を手に入れたい方におすすめの一冊です。
アドラーに学ぶ どうすれば幸福に生きられるか
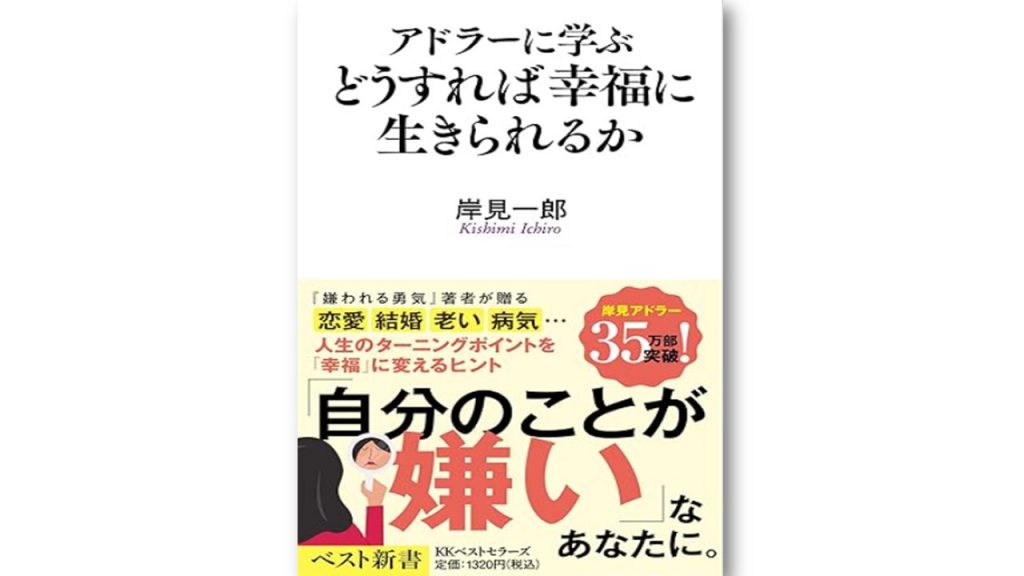
「アドラーに学ぶ どうすれば幸福に生きられるか」は、人生の悩みをアドラー心理学で解決するための実用的な指南書です。
著者の岸見一郎氏は、自己肯定感や人間関係、老い、病気、死といったテーマに具体例を交えて解説しています。
「自分が嫌いなのは他者との関わりを避けているから」というように、悩みの原因と解決の糸口を明確に示してくれるのが特徴です。
また、「結婚生活が成功する秘訣」や「老後の無力感への対処法」など、人生のさまざまなステージに役立つアドバイスが多くあります。どんな年代の読者にとっても幸せへのヒントを見つけられる一冊です。
また、今回ご紹介したアドラー心理学の本を通じて、人間関係をより良くしたいと感じた方には、こちらの記事がおすすめです。人間関係の悩みを解消し、円滑なコミュニケーションや信頼関係を築くための本を厳選して紹介しています。
アドラー心理学のよくある質問
アドラーとフロイトの違いは?
アドラー心理学では、現在の目標や価値観が個人の行動や人格形成に大きな影響を与えると考えています。
フロイト心理学では、過去のトラウマや無意識の欲求が個人の行動や感情に大きな影響を与えると説いています。
フロイトについては以下の記事も参照してください。
■ 合わせて読みたい
> 心理学の巨匠フロイトとは|経歴や思想をわかりやすく解説
アドラーとユングの違いは?
アドラー心理学は、個人が自己実現や目的達成のために行動するプロセスにフォーカスしています。
一方、ユング心理学では、個人の内面におけるアーチタイプ(普遍的な心理的要素のこと)や集合的無意識についての研究に焦点を当てています。
ユングについては以下の記事も参照してください。
■ 合わせて読みたい
> ユング心理学を分かりやすく解説!フロイトとの違いもご紹介
アドラー心理学のデメリットってなに?
アドラー心理学では、個人の内面にフォーカスし過ぎることがデメリットの一つとして考えられています。
自分個人の問題を解決しようとする際に社会的な要因や背景を無視するため、個人の問題や病気に対するアプローチには限界があるとされています。
まとめ
アドラー心理学とは、心理学の世界三大巨匠の一人であるアルフレッド・アドラーが提唱した思想です。
別名「勇気の心理学」とも呼ばれ、アドラー心理学を活用すれば、自分を変え、理想に近づくために必要な「勇気」を引き出せます。
例えば「課題の分離」を実践すれば、他人の期待や評価に振り回されることなく、自分の課題に集中できるようになります。
このシンプルで力強い理論は、仕事・恋愛・人生すべてにおいて役立つでしょう。
また、アドラー心理学は、マーケティングに強い組織作りにも応用可能です。
例えば、「共同体感覚」や「他者への関心」を重視する考え方を取り入れることで、お客さまや社員の特性を理解し、相手が本当に必要としている提案やサポートを的確なタイミングで行えるようになります。
このアプローチによって、信頼関係を深め、相手のニーズに応じた行動が取れるようになるため、成果を上げ続けられる組織ができるのです。
セミナーズ運営会社であるラーニングエッジでは、こうした組織作りをサポートする「マーケティングに強い組織作りの秘訣」をまとめた無料の資料を提供中です。
すでに多くのリーダーの方にご活用いただいており、部下の能力を引き出しながら、理想的な組織作りを実現したい方は、ぜひご覧ください。