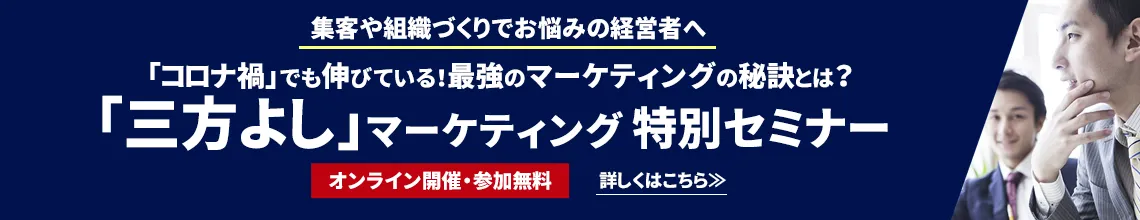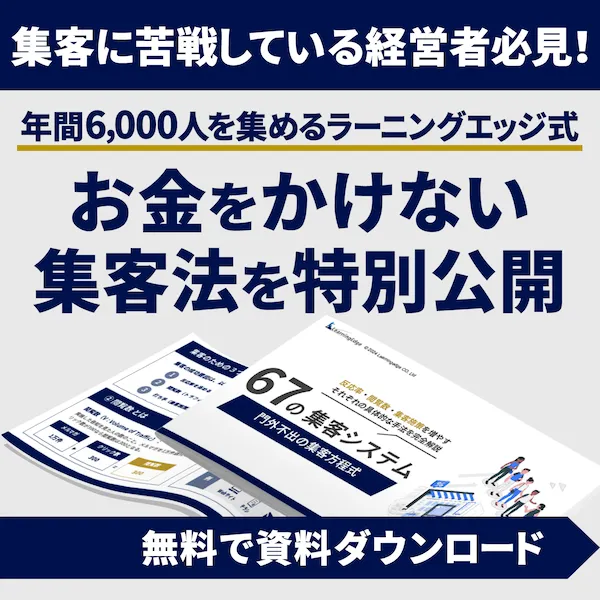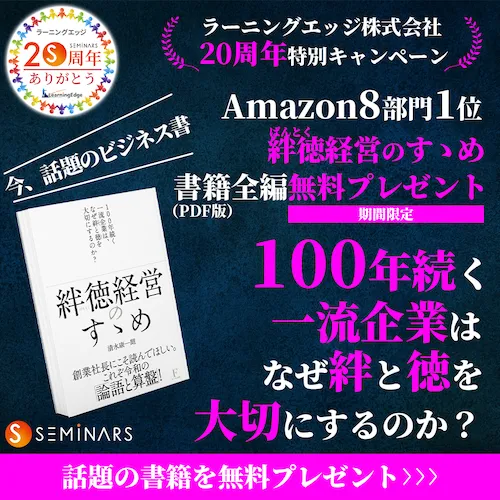PDCAサイクルが古いと言われる理由は、「PDCAは時間がかかるから」「PDCAそのものが目的になりがちだから」の2つです。
業務効率を飛躍的に上げて生産性を高める手法は、PDCAだけではありません。
激しい状況変化に対応できるOODAや短期間でおこなえるPDRなど、自社の業務や方針に合った手法を取り入れることで、解決できる可能性があります。
この記事ではPDCAについて振り返りながら、古いといわれている理由、PDCA以外のフレームワークについて紹介します。
PDCAを取り入れ、思うように成果が出ないとお悩みの経営者の方は、自社の生産性アップに効果的な手法選びの参考にしてみてください。
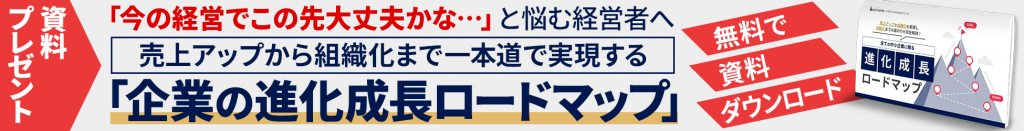
PDCAが古いといわれる理由

PDCAが古いといわれる理由はおもに次の2つです。
- PDCAは時間がかかる
- PDCAそのものが目的になりがち
品質管理や業務の改善を図るために有効なPDCAですが、流行やニーズの変化が激しい近年は「古い手法」といわれることがあります。では、具体的な理由について解説します。
PDCAは時間がかかる|長期的に品質を管理するための手法
PDCAは、長期的に品質を管理して改善をするための手法です。業務改善に有効なフレームワークとして、製造業やIT業界、医療業界など、幅広い分野の企業が活用しています。
PDCAは、以下の4つのプロセスを1セットとしてサイクルする手法です。
- Plan:計画
- Do:実行
- Check:評価・検証
- Action:対策・改善
計画から実行までを1つのプロセスとしているため、実行すべき内容が明確になります。評価・検証の際も、何に着目すべきか分析しやすいでしょう。
ただし、PDCAは計画から実行までに時間がかかります。
近年は流行やニーズが変動しやすく、計画を立て実行するときには状況が変わっていることも少なくありません。そのため、実行の先にある評価・検証ができず、改善まで進まないことがPDCAが古いといわれる理由です。
PDCAは計画を実行してから、評価・検証をおこない、対策と改善まで進んで1セットです。計画と実行だけでは、プロセスの半分しかできていません。
PDCAは長期的な業務の改善には適していますが、短期的に成果を出す手法としては不向きです。
PDCAそのものが目的になりがち|目標・期間を明確にすることが大切
PDCAが古いといわれている理由として、PDCAというフレームワークそのものが目的になりがちなことが挙げられます。
計画を立案し、実行するためにはコストがかかります。結果とコストのバランスが取れていなければ、業務ではなく計画のためにお金をかけていることになります。
PDCAは業務の品質管理と改善を目的とした手段です。PDCAサイクルがうまく回せていないと感じているなら、目標と期間を明らかにすることを意識しましょう。
何のためにPDCAをおこなっているのかを明確にすることで、現状の課題が分析しやすくなり、結果的に品質管理、改善につながります。
PDCAのメリット・デメリット
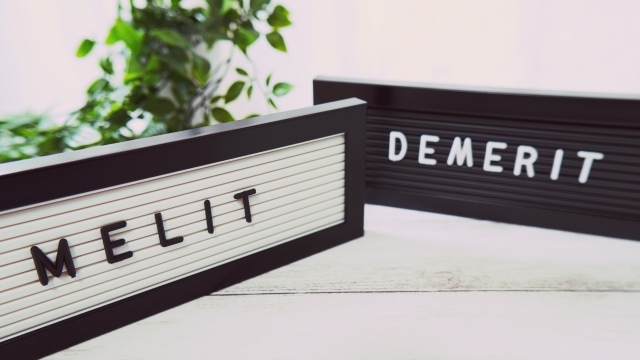
PDCAは業務担当者のスキルアップが見込めるというメリットがある一方、新たな発想が生まれにくい点がデメリットといえます。では、PDCAのメリットとデメリットについて、それぞれ詳しく解説します。
メリット|業務担当者のスキルが向上する
PDCAのメリットは、目標達成のために必要なスキルの向上ができることです。業務の目標、改善策が明確になるため、業務担当者の自主性、応用するスキルを養えます。
業務担当者は自分の経験から成功、失敗の要因を学ぶ能力を習得。今後の失敗に備えられ、他の業務にも経験を活かせます。
また業務の問題点を浮き彫りにする点もPDCAのメリットです。
デメリット|新たな発想が生まれにくい
PDCAのデメリットは、新たな発想が生まれにくいことです。PDCAは前例をもとに評価を行い、改善策を実行するというサイクルを繰り返すため、どうしても過去のデータありきの発想が増えがちです。
たとえば突発的なトラブルへの対処や、新たなクリエイティブの制作において、PDCAは適していません。これまでとは異なるアイデアを見つけるためには、さまざまな意見に耳を傾けたり、他の事例に目を向けたりする必要があります。
PDCAをもっと活用したり、チームで連携して目標達成していきたいという方は、ぜひこちらの無料でご覧いただける資料をお受け取りください。
PDCAサイクルの改善に取り組むための具体的な手順
PDCAサイクルの改善に取り組むためには、以下の3点について取り組んでみましょう。
- 問題を洗い出す
- 改善案を立案する
- 評価する
1. 問題を洗い出す
PDCAサイクルにおける「P(計画)」フェーズでは、まず問題を洗い出すことが重要です。
そのためにも情報を集め、問題の原因や影響範囲を明確にしておきましょう。
例えば、製品に不良が多い場合は、不良品の数や顧客からの苦情などを分析することができます。顧客からのフィードバックも重要です。
また、社内のデータだけでなく、市場調査などの結果も積極的に活用します。
問題の洗い出しを行う上で大切なのは、関係者が協力して行うことです。関係者からの意見に耳を傾けると、問題点をより明確に把握できます。
2. 改善案を立案する
PDCAサイクルにおける「P(計画)」フェーズで問題点が明確になったら、改善策を立案します。
改善策は、問題点や原因に応じて、具体的かつ実行可能なものを選びます。改善策決定の際には、関係者からの意見を取り入れましょう。
改善策を選ぶためには、以下の点に留意することが大切です。
・改善策が実行可能であるか
・改善策の効果を確認するためにどのような指標が必要か
・改善策を実施するために必要なリソースや時間はどれだけか
改善策を立案する際には、アイデア出しのセッションやブレスト、SWOT分析、フォーカスグループインタビューなど、様々な手法があります。
3. 評価する
PDCAサイクルにおける「Do(実施)」フェーズで、改善策を実施し、その結果を評価します。
改善策を実施する前に、計画的な実施のためのロードマップを作成することが重要です。
改善策を実施した後には次のような項目を評価基準にすることがあります。
- 計画通りに実施されたか
- 目標が達成されたか
- 予期せぬ問題が発生しなかったか
その結果をもとに、PDCAサイクルの「Act(改善)」フェーズに進むか、再度「Plan(計画)」フェーズに戻るかを決定しましょう。
PDCAサイクルを効果的に活用するための3つのポイント
PDCAサイクルを効果的に活用するためのポイントは、以下の3つです。
- 目標設定を明確にする
- 報告と共有
- 継続的な改善を行う
1. 目標設定を明確にする
PDCAサイクルにおいては、改善の目的や目標を明確にすることが重要です。
具体的な目標を設定することで、改善の方向性を明確にし、改善効果を確認しやすくなります。目標は、5つの要素をもとに目標達成の可能性を高めるフレームワークである「SMARTの法則」を使って考えるとスムーズです。
- Specific(具体的)
- Measurable(測定可能)
- Achievable(実現可能)
- Relevant(関連性がある)
- Time-bound(期限付き)
この5つの要素を満たす目標を立てると、やるべきことが明確になり、モチベーションが維持しやすいといわれています。
SMARTの法則についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
2. 報告と共有
PDCAサイクルを効果的に活用するためにも、改善の進捗状況を随時報告し、関係者と共有することを意識しましょう。
報告と共有を行うことで、お互いにフォローしあったり、新たな気づきが生まれたりします。
また、定期的に進捗を共有することで、抜けや漏れなどのミス防止にもつながります。
3. 継続的な改善を行う
PDCAサイクルを効果的に活用するためには、継続的な改善を行うことが必要です。
PDCAサイクルは、一度だけ回すだけでは効果が薄く、繰り返し行うことによってブラッシュアップが見込めるフレームワークです。
継続的な改善を行うためには、定期的なPDCAサイクルの実施や、関係者の協力が必要になります。また、改善の効果を定期的に評価し、必要に応じて改善策を修正するのも重要なポイントです。
PDCAに代わるものといわれる3つの手法と特徴

業務の生産性アップを図る手法は、PDCAだけではありません。
これから紹介するPDCA以外のフレームワークは、以下の3つです。
- OODA
- DCPA
- PDR
以下を参考に、自社に合ったフレームワークを取り入れてみてください。
OODA|激しい状況変化に対応できる
OODA(ウーダ)とは、以下4つの頭文字をとったフレームワークです。
- Observe:観察
- Orient:状況判断・方針決定
- Decide:意思決定
- Act:行動
OODAは観察からスタートすることで、現状を分析します。その方針を軸にした意思決定をおこない、実行に移るプロセスです。
OODAは状況変化が著しい業務に適しており、OODAを取り入れることで、消費者のライフスタイルや価値観の多様化に適応可能です。
PDCAのサイクルに対し、ループするという考え方のOODAは、観察から行動まで素早くおこなえます。
計画を立て、実行して改善するPDCAに対し、OODAは現状を観察することからスタート。課題がわかった時点で行動します。
1.Observe(オブザーブ):観察
OODAは、最初のObserve(オブザーブ)で対象を観察し、現在の課題やデータ収集をおこないます。
Observeとは、固定概念に固執せず、自分以外の外部状況に関する情報を収集する段階のことで観察や監視と訳される言葉です。
引用元:カオナビ|人事用語集
観察対象は以下を参考にしてください。
- 品質管理
- 市場
- 競合
まずは、これらを観察し正確なデータを収集します。
2.Orient(オリエント):状況判断・方針決定
Orient(オリエント)では、Observeで収集したデータに基づいて状況を判断し、方針を固めます。
Orientとは、Observeの段階で収集したデータをもとに「判断価値を含んだインフォメーション」として生成する段階のこと。
引用元:カオナビ|人事用語集
こまかな計画を立てるのではなく、ひとまず仮説として立案し方向づけをおこないます。過去の判断に誤りがあれば、それに気づき正すことが重要です。
3.Decide(ディサイド):意思決定
Decide(ディサイド)では、1.Observe(観察)と2.Orient(状況判断・方針決定)によって出した仮説を確認します。
実際の効果や影響があると判断した仮説を選択し、次の4.Act(行動)を具体化するために、今後の方針を決定します。
4.Act(アクト):行動
Act(アクト)では、3. Decide(意思決定)で採用した選択に基づいて、実際に行動します。
OODAは、常に状況変化を意識しながら取り組む手法です。もし判断に迷ったり状況が変わったりしたときは、1のObserveまで戻って繰り返し取り組んでみましょう。
DCAP|ニーズに合わせやすくスピーディ
DCAPはPDCAと順番が異なりますが、内容は同じです。
- Do:実行
- Check:評価
- Action:改善
- Plan:計画
実行からスタートするDCPAは、ニーズに合わせて立案しやすくスピーディな手法です。
しかし、サイクルを何度も繰り返さなければ成果が見込めません。そのため、途中で方針を変更すると費用がかかるような、大規模なプロジェクトには不向きです。
PDCAとDCAPの大きな違いは、目標を立てる順序です。計画を立て、実行して改善するPDCAに対し、DCAPは行動からスタートして最後に改善計画を立てます。
トライアンドエラーを繰り返すため、無駄が生まれやすいというデメリットがありますが、アウトプットをメインとした手法なので課題が見つかりやすいのが特徴です。
PDR|スパンが短く汎用性が高い
PDRは、スピーディに遂行したい業務に適したフレームワークです。スパンが短いため、どのような用途にも素早く対応できます。
PDRのプロセスは以下の3つです。
- Prep:準備
- Do:実行
- Review:評価
PDRのPはPrep(準備)です。これから何をすべきか、理由や目的を考えます。
Dは、PDCAと同様に実行を意味するDoです。1のPrep(準備)で考えた内容に沿って、行動をおこします。
最後のRはReviewです。評価と訳される点はPDCAのCheckと同じですが、意味が異なります。
PDCAのCheckは、ミスや不正がないかを確認する作業です。それに対しPDRのReviewは、業務担当者以外の人に成果を見てもらい、客観的に評価をもらうことを指します。
PDRは一度のスパンが短いため、PDCAよりも時間がかからないというメリットがあります。また早い段階で課題を発見できるので、小さな変化やトラブルにも対応しやすいのが特徴です。
移り変わりが激しい近年だからこそ、短いスパンで繰り返せるPDRは時代にマッチした手法といえるでしょう。
フレームワークを使い分けて生産性アップを目指そう
PDCAは古いといわれていますが、長いスパンでつくり上げるビジネスには有効なフレームワークです。必ずしも通用しないわけではありません。
もしPDCAがうまく回せていないと感じているなら、プロジェクトごとにフレームワークを使い分けてみてはいかがでしょうか。
激しい状況変化に対応する業務ならOODA。短期的に成果を求める業務であれば、短いスパンで繰り返すPDRを試してみましょう。
ただ、フレームワークはあくまでも手段です。自社の生産性を上げるなら、フレームワークだけにこだわるのではなく、結果にもこだわれるものをテストしながら選んで取り組むようにしてみましょう。
こちらの無料の資料は、この記事をご覧になった方にオススメな、実際に事業を拡大していくための考え方をまとめたものになっております。ぜひ受け取っていただき、自社のフレームワークの洗練にお役立てください。

#PDCA #OODA #DCAP #PDR