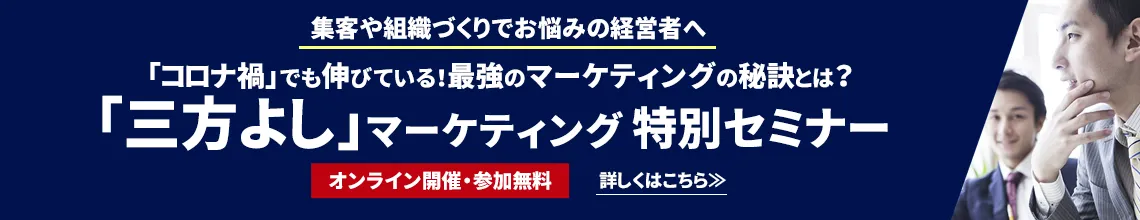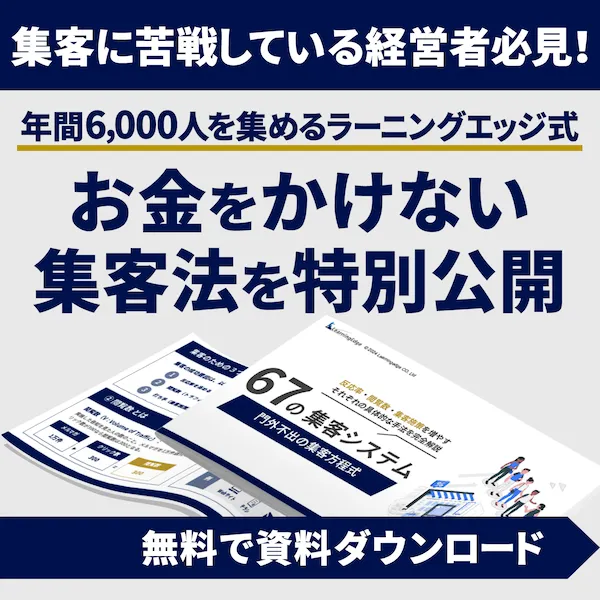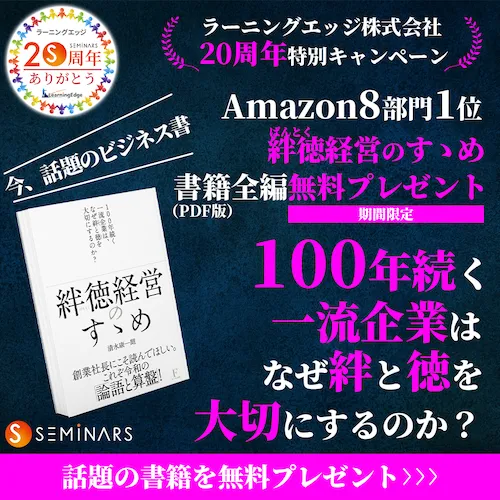成果主義とは、社員が仕事で出した結果や成果で評価し、それを元に給料や昇進を決める制度のことです。
- どうして成果主義が増えているの?
- 成果主義のメリット・デメリットを教えてほしい
- 成果主義導入のポイントって何がある?
この記事ではこういった疑問にお答えしていきます。
年功序列制度から切り替えて成果主義を取り入れていきたい…と考えている人事担当者は参考になさってください。
成果主義とは?
成果主義は、社員が仕事で出した結果や成果で評価し、給料や昇進を決める方法です。成果主義では、年齢や学歴、勤続年数などは評価の対象外となります。最も重要なことは、社員が会社のためにどれだけの成果を出したかです。
例えば、売り上げを多く上げた人や企業の良い未来につながるアイデアを出した人は、さらに昇給・昇進することが多くなります。ただ長く会社にいるだけでは、特別な報酬は期待できません。
成果主義は、社員がさらに頑張りたくなる仕組みを作ることを目指しています。しかし、社員の仕事量が多くなったり長時間働くことが増えたりすることもあるので、上手にバランスを取ることが大事です。
成果主義と年功序列制度の違い
年功序列制度は、社員が会社にいる年数や年齢を重視して評価します。
社員が会社に長く勤めることで自然と昇給や昇格が期待できるため、安心して長く働ける環境を作ります。
一方、成果主義は社員の成果や業績に基づく報酬を重視するため、仕事に対するモチベーションを高められるのです。
成果主義と能力主義の違い
能力主義は、社員の持っている知識や能力、さらには態度までを考えて評価する方法です。成果主義は「仕事」に注目し、能力主義は「人」つまり、社員の能力に焦点を置きます。
例えば、成果主義では目標を達成したり売り上げを増やしたりした社員が報酬アップや昇進のチャンスをつかめます。
一方、能力主義では優れた資格を持っていたり特定の技能を磨いていたりする社員が評価されるのです。
成果主義のように即座に成果を出すことが求められることは少ないといえます。
成果主義が広まった背景
次に、成果主義が広まった背景を紹介します。
バブル崩壊が導入のきっかけ
1990年代のバブル崩壊後、日本の企業は経済の停滞を乗り越えるために社員の給料の決め方を変えざるを得なくなりました。その時に注目されたのが、成果主義です。
長い間日本の会社では年功序列が主流でした。つまり、働いている年数が長いほど給料が上がっていきます。しかし、バブルがはじけて不景気になると年功序列制度では会社の経費がかさむばかりです。
そこで、より効率的な給料の決め方として成果主義が取り入れられ始めたのです。
例えば、富士通は1993年に成果主義を取り入れた会社の一つです。成果主義は、会社の経費を抑えつつ、社員にやる気を出させる新しい方法として浸透していきました。
働き方改革の推進により一般的に
成果主義は、2019年に「働き方改革関連法」が施行されて以降さらに広まりました。
働き方改革では、残業時間が原則として月45時間・年360時間までの上限が設けられ、企業は社員の時間を有効に使うことが求められるようになりました。
これにより、ただ長時間働くのではなく、どれだけ効率よく成果を出せるかが重視されるようになったのです。
このような変化から、多く企業はより成果を出した社員を評価する成果主義を取り入れるようになりました。成果主義は働く人々のやる気を引き出し、企業の生産性を高める方向に進んでいます。
成果主義のメリット
次に、成果主義のメリットを紹介します。
質の高い人材育成や人材確保
成果主義は成果が昇進や給与アップに直結するため、社員は自分のスキルを磨くのに積極的になり質の高い人材育成ができます。
また、優秀な人材が見落とされにくく必要な人材をしっかりとつなぎとめられるのもメリットです。
年功序列の場合、勤続年数が功績に勝ります。しかし、成果主義なら実際の仕事の成果が直接評価されるため優秀な人材が光るチャンスが増えるのです。
生産性の向上
成果主義を取り入れると、社員は成果を早く出すために仕事のやり方を効率よくする工夫をします。
社員は大切な仕事に時間を多く使うため、必要のない仕事は省くようになるのです。
例えば、ある会社が成果主義を採用したとしましょう。その結果、社員が報告書を作る時間を半分に削減しました。残った時間は、新しいアイデアを考えることや顧客との話し合いに使えるようになります。
社員は成果主義を取り入れるとより企業の売り上げや仕事の成果に直結する業務に時間を割くようになり、生産性が向上するのです。
モチベーションの向上
成果主義は、成果を公平に評価して社員のやる気を引き出します。
立場に関係なく実際に出した成果が評価対象となるため、若手社員も活躍できる場が広がるのです。
結果として、社内競争が生まれよい意味での切磋琢磨が促されます。
例えば、ある新入社員がプロジェクトで特別な成果を出したとします。成果主義の会社ではその成果がすぐに認められ、特別な賞や昇進、報酬の増加などで評価されるでしょう。
成果主義の取り組みは、当事者にはもちろん周囲の社員にも「頑張れば結果が出る」というメッセージを送り、皆のモチベーションを高められます。
人件費の最適化
成果主義は社員の実際の成果で給与が決まるため、会社の人件費をより合理的に管理できます。
年功序列制度では長く働けば働くほど給料が上がるため、業績に関係なく人件費が増えるのです。一方、成果主義では、年齢ではなく成果で給与を決めるため不必要な人件費の増加を防げます。
また、成果主義では業績に応じた公平な報酬を社員に支給できます。
例えば営業部門のある社員が年間の販売目標を大きく超えた場合、成果主義ではその成績に応じて特別なボーナスが支払われます。一方で、目標に達しなかった社員はその年のボーナスが少なくなるのです。
成果主義は社員に対して成果をもとにした公平な報酬を払い、企業は会社の人件費も無駄なく管理できます。
成果主義のデメリット
次に、成果主義のデメリットを紹介します。
評価基準の設定が難しい
異なる部門の仕事を比較することは複雑であり、公平で正確な評価基準を設けるのが難しいです。
職種によっては成果が目に見えないこともあるため、それぞれの仕事内容に合った評価基準が必要となります。
例えば、法務部門の社員がリスクを防ぐための重要な提案をしたとします。この成果はすぐには数字に表れませんが会社にとっては非常に価値があるものです。
数値で表せない成果や長期的な貢献を評価するのは容易ではありません。
チームワークが発揮されない
社員がチームよりも自分の業績を優先して、組織としての協力や一体感がなくなることがあります。
周囲との競争が過度になると助け合いや情報共有が減り、チーム内の協調性が落ちるのです。
例えば、営業部門でチームと個人の目標がある場合、個人の成果が高く評価されると他のメンバーと協力するより自分の成績を上げるのに集中する社員が出てきます。その結果、チームとしての大きなプロジェクトや目標が達成できない可能性があるのです。
離職率が増加する
高い成果が求められる圧力で社員が大きなストレスを感じ、離職率が増える場合があります。
社員は望む結果が得られないと、やる気が落ちて最終的に会社を去ることがあるのです。
例えば、営業部門で成果主義により月間売り上げの目標が厳しく設定されているとします。
目標を達成できなかった社員は、給与のカットや役職の降格を経験するかもしれません。このような状況は、ストレスを感じた社員が他の仕事を探して会社を去る原因です。
成果主義を導入するポイント
次に、成果主義を導入・実践するポイントを解説します。
評価基準を明らかにする
企業が成果主義を取り入れるには、達成可能で明確な評価基準を作ることが大切です。
評価者によりばらつきが出ない評価項目を設定し、透明で分かりやすく社員が納得感を持てる評価基準を作ってください。
例えば、目標達成度に基づく評価であれば、営業職の場合四半期ごとの売り上げ目標達成率を評価基準にできます。目標の100%達成で基準点、それ以上達成で加点、未達成で減点するシステムを採用する方法です。
評価基準は定期的に見直し、社員からの意見を取り入れることでより公平で納得できるものにしましょう。
定量・定性評価を設定する
成果主義では、数値で測れる業績(定量評価)だけでなく、数値にできない部分(定性評価)の両方をバランスよく評価する能力が必要です。
公平な評価をするためには職種や部署ごとの具体的な役割や目標を理解し、それに基づいた定量・定性評価基準を設定しましょう。
例えば、あるIT企業のプロジェクトマネージャーの評価プロセスであれば、プロジェクトの納期遵守(定量的)だけでなく、チーム内のコミュニケーションや問題解決能力(定性的)も評価対象に含められます。
報酬体系の設定
社員の業績に応じた適切な報酬水準を検討し、設定しましょう。高い業績を上げた社員へは、さらにモチベーションを上げるためにインセンティブを支給するとよいです。
ボーナスや歩合制などの報酬オプションを取り入れると社員は自らの努力が報われると感じ、より成果を出すために努力します。
例えばボーナス制度であれば、年間の業績目標を達成した社員にはその成果を反映したボーナスを支給します。目標を超えた場合の追加ボーナスも設定し、より高い成果を目指す動機づけにするとよいです。
社員には報酬体系とその詳細をはっきりと伝え、自分の業績が報酬にどのように影響するかを理解してもらいましょう。
評価者の育成
評価者を育成して評価基準を正しく理解させ公平な評価を行ってもらうことは、社員が安心して仕事に取り組むために重要です。
具体的には、評価者向けの研修プログラムを設けて、適切な評価基準の理解や公平な評価方法について教育を行います。事例をあげて説明しながら、客観的な評価の方法を理解させることが重要です。
また、評価者の能力やスキルに応じた個別指導やメンタリングを行い、評価者が自己成長できる環境を整えましょう。
成果主義の実践事例
最後に、成果主義の成功例と失敗例を紹介します。自社で取り組む際の参考にしてください。
成功例:花王
花王は社員が納得感を持って働ける評価基準を設定し、成果主義を成功させています。
職務や部門ごとに特性を考慮した「職群制度」を設け、それぞれに合った公平な評価基準を導入しました。
例えば、研究部門の社員は短期間での成果だけでなく長い目で見た研究の進捗も評価されます。生産部門では作業のスピードだけではなく、どれだけ上達したかも考慮されるのです。習熟度を含め多面的な評価をします。
花王は評価基準のぼやけをクリアにし、部門や職務の特性に応じた適切な評価を行うことで成果主義を導入しました。
成功例:武田薬品工業
武田薬品は業績に連動して給与が変わる成果主義の人事制度を導入して、企業の売り上げと利益を大きく伸ばしました。
この取り組みでは評価基準をクリアに設定し、社員の業績がどのように評価され報酬に反映されるかを詳細に共有しました。その結果、社員は自分の仕事にもっと集中してチーム全体の成果にも貢献するようになったのです。
武田薬品工業は社員一人ひとりが自分の役割を理解し、それに対する適正な報酬を与える制度を作り導入を成功させました。
失敗例:三井物産
三井物産は成果主義の賃金制度を1999年に導入しましたが、かえって企業成長が阻害された企業例です。
成果主義を導入して以降、三井物産では社員間の協力よりも個々の成績を競う風潮が強まりました。これが、特に若手社員の育成を阻害し、長期的な企業の成長に悪影響を与えたのです。
また、成果主義が原因で、社員の成長意欲ややる気が低下する事態も発生しました。
三井物産は2006年には成果主義の賃金制度を見直し、チームワークと人材育成を優先する制度へと戻しています。
失敗例:日本マクドナルド
日本マクドナルドは成果主義の導入により競争を促しましたが、それが経験豊かな社員の若手の育成を疎かにする結果を招きました。
日本マクドナルドでは定年制を廃止して成果主義を導入し、実力本位の意識を高めようとしました。しかし、導入後はベテラン社員が個々の成果を出すことに注力しすぎて、若手社員への指導が不足してしまったのです。
これにより、若手の育成が不十分となり組織全体の成長にも影響を与えました。日本マクドナルドは制度の見直しと定年制の復活を余儀なくされています。
成果主義の導入は評価基準の設定から
今回は、成果主義の概要や年功序列制度と能力主義の違いや行うポイントや実践事例などを紹介しました。
成果主義は、年齢や学歴、勤続年数などで評価せず、純粋な仕事で出した成果のみを評価するものです。
成果主義を導入する際は、評価者によってばらつきがなく、社員が納得感を持てる評価基準を明らかにすることから始めましょう。企業事例を参考にしながら、慎重に導入を進めてみてください。
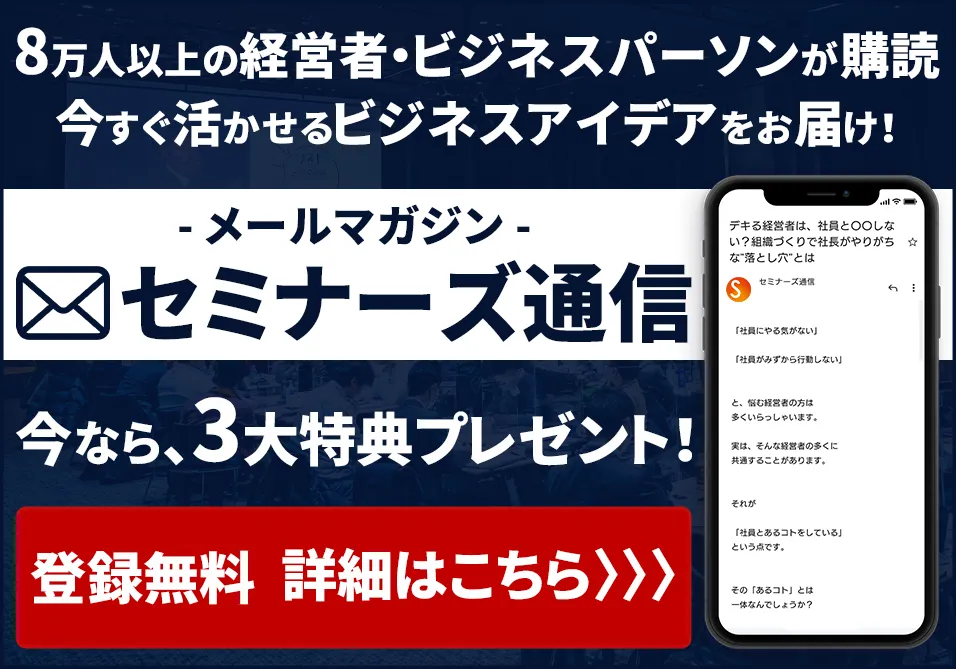
年商5億円を超えさらなるスケールアップを目指す経営者必見!
あなたのビジネスをスケールアップさせる集客と組織作り、
さらに、成功事例やここだけのお得な内容をお届け致します。