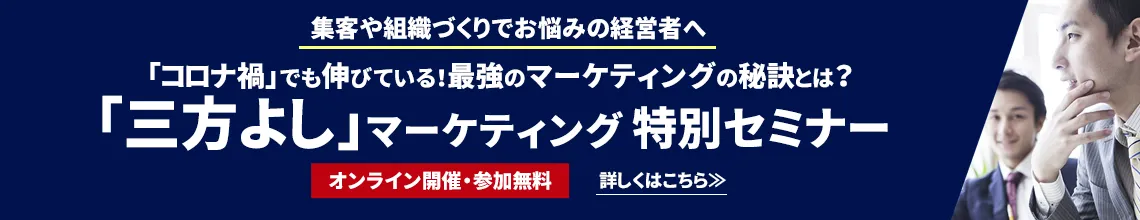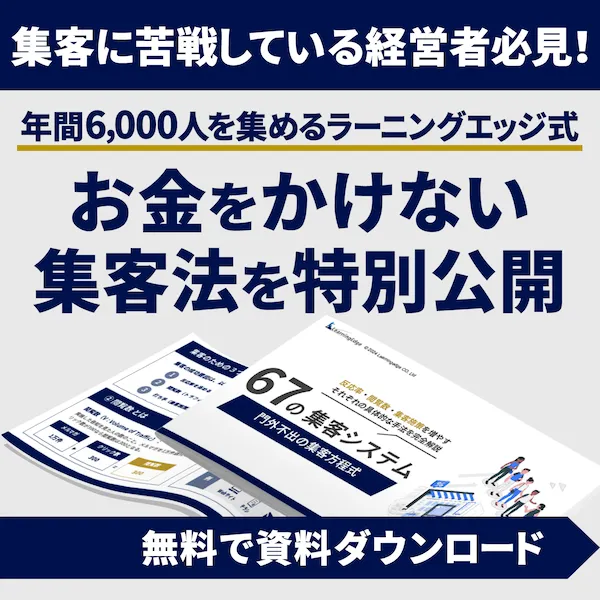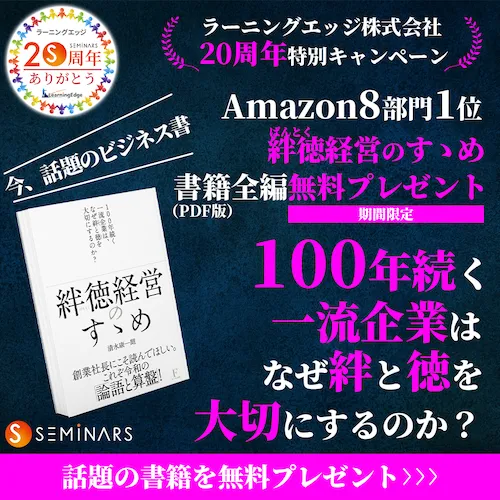アドラー心理学を学んでマネジメントに活かすことで、伸び悩む部下をどうしたら成長させることができるか指標を明確にできます。
モチベーションを上げる方法や、正しい褒め方なども見つかりやすくなるため、管理職・リーダー層にこそ身につけていただきたい心理学です。
今回は、マネジメントの極意ともいえるアドラー心理学の理論を紹介します。
部下や従業員の育成・管理に悩んでいた方々にとって、悩みを解決する重要なヒントとなるかもしれません。
マネジメントに役立つアドラー心理学の3要素
アドラー心理学とは、心理学の三大巨匠の1人とされるアルフレッド・アドラーが提唱した理論のことです。
2013年に発刊された書籍『嫌われる勇気』がベストセラーとなり、アドラー心理学が広く知られるようになりました。
実は、アドラー心理学にはマネジメントの極意ともいえる本質的な要素が含まれています。
特に押さえておきたいのが、次に挙げる3つの要素です。
1. 課題の分離
アドラー心理学の有名な理論の1つに「課題の分離」があります。
課題の分離とは、他人の課題と自身の課題は本質的に異なるものであり、介入しない・させないことが重要という考え方です。
人間関係におけるトラブルの大部分は、自身の課題と他人の課題が区別できなくなっていることに起因するとアドラーは考えました。
一例として、次のような場面をイメージしてみましょう。
- 部下が仕事でミスをしたため、部下とともに原因を特定し再発防止策を考えようとした。
- きつい言い方をしたつもりはなかったが、部下はひどく落ち込んだ様子だった。
上記のような場面に遭遇した時、皆さんはどのような感情を抱くでしょうか。
知らず知らずのうちに言い方がきつくなっていたのかもしれない、と反省する人も多いでしょう。
課題の分離にもとづいて考えた場合、部下が上司の言葉をどう捉えるかは部下自身の課題であり、上司は介入できません。
部下は「失敗した時は落ち込むものだ」と思い込んでおり、意気消沈した様子を見せたのかもしれないのです。
2. 承認欲求の否定
承認欲求とは、他人から認められたい・自分の価値を認めて欲しいという欲求のことを指します。
裏を返せば、誰かの期待に応えたいという思いが承認欲求の正体ともいえるでしょう。
アドラー心理学では承認欲求を否定し、他人の期待を満たすために生きることを危険視しています。
承認欲求は「適切な行動を取れば褒められる・不適切な行動を取れば罰せられる」という賞罰教育の結果と捉えているからです。
賞罰教育にもとづく価値観は、次のような誤った行動を誘発するリスクを孕んでいます。
- 適切な行動をとっても褒められない→今後は適切な行動を取る必要はない
- 不適切な行動をとっても罰せられない→今後は不適切な行動も許される
自身の行動を他人の反応にもとづいて選択しているために、誤った判断・行動につながりかねないのです。
上司と部下、経営者と従業員の関係においても、相手の承認欲求を満たすための言動には注意する必要があります。
3. 勇気づけ
アドラー心理学は「勇気の心理学」と呼ばれることもあるほど、勇気づけを重視しています。
勇気づけとは、相手の行動や発言を含めたプロセス全体を肯定し、認めることに他なりません。
たとえば、子どもがテストで高得点を取った時、親としてどのように声掛けをするのがよいのでしょうか。
- すごいね!次回のテストも同じように高得点を目指そう。
- 頑張った甲斐があったね。次回もきっと高得点を取れるよ!
1は一見褒めているようでいて、実は子どもが持ってきたテストの「結果」を評価しています。
子どもとしては、次も同じように高得点を取らなくてはならないというプレッシャーを感じるでしょう。
一方、2は高得点に至るまでの努力を評価し、頑張ったからこそ高得点につながったと伝えています。
子どもとしては、今回と同じように頑張れば次回も高得点を取れるかもしれない、と勇気づけられるでしょう。
言葉の背後に「勇気づけ」の要素があるかどうかによって、伝わり方は大きく変わるのです。
課題の分離を応用したマネジメントの例
課題の分離を応用したマネジメントの例を紹介します。
部下や従業員が抱えている課題と、上司や経営者自身の課題はそもそも分けて捉えてことが重要です。
マネジメントに課題の分離を応用するとしたら、どのような対応が考えられるのでしょうか。
営業成績が伸びない部下をどう伸ばすか?
毎日せわしなく動き回っているにも関わらず、営業成績が一向に伸びない部下がいたとします。
全員がエース社員というわけにはいかない以上、伸び悩んでいる部下を伸ばし、育てるのも上司としての役割です。
一方で、上司の視点から見た場合、「なぜ契約が取れないのか?」が理解できないケースが少なくありません。
結果として、活動量を増やすようアドバイスをしたり、プレッシャーをかけて部下を追い込んだりしがちです。
よくある誤った対応例
営業成績が伸びない部下に対する、よくある誤った対応として次のものが挙げられます。
- 「なぜできないのか」と相手を責めてしまう
- 結果が芳しくないことについて叱責してしまう
- 不機嫌な様子を見せる
- 目標やノルマを提示してプレッシャーをかける
- 具体的な活動内容を根掘り葉掘り聞いてしまう
部下の立場としては、上司から介入されればされるほどプレッシャーを感じ、萎縮してしまうでしょう。
結果として、パフォーマンスが低下しますます成果につながりにくい状況に陥る可能性があります。
営業成績が思わしくないという部下の課題に、上司が介入しようとすることで事態を悪化させてしまうのです。
課題の分離にもとづく対応例
課題の分離にもとづいて対応するなら、「部下自身に課題を見つけてもらう」のが得策でしょう。
具体的には、1on1の場を設けて次の点を部下に質問していきます。
- 現状を自分自身はどのように捉えているか?
- 本来はどのような結果を望んでいるのか?
- 理想と実態にギャップが生じているのはなぜだと思うか?
- ギャップを埋めるにはどのようなアクションが必要になるか?
質問に答えてもらうことが目的ではなく、質疑を通して部下自身の課題を整理してもらうことが真の狙いです。
上司が「〇〇したほうがいい」と一方的にアドバイスしても、部下自身の課題として捉えられない可能性が高いでしょう。
課題の分離にもとづいて対応するなら、部下が自身の課題に気づき、自ら解決を目指す方向へと向かうよう導くことが重要です。
承認欲求の否定を応用したマネジメントの例
次に「承認欲求の否定」をマネジメントに応用する方法を考えていきます。
部下を「褒めて伸ばす」という言い方がありますが、「褒める」のは部下を育成する上で本当に効果的なのでしょうか。
部下を褒めても伸びないのはなぜか?
部下のモチベーションを高めたい・意欲を引き出したい上司の中には、部下を意識的に褒める人がいます。
事あるごとに部下を褒めているにも関わらず、部下が一向に成果を挙げない・伸びないといったケースは少なくなりません。
実は、部下を褒めているからといって部下の能力やパフォーマンスが向上するとは限りません。
褒める場合にも「褒め方」を誤ってしまうと、部下の承認欲求を誤った方向に導く恐れがあるからです。
よくある誤った対応例
新たな企画の社内プレゼンを部下に任せた場合を考えてみましょう。
プレゼンに説得力があり、資料も十分に練られたものになっていた場合、上司は部下を次のように褒めるかもしれません。
- プレゼン、すごく良かったよ!
- 説得力のある、引き込まれるプレゼンだった!
上司からプレゼンを褒められた部下は、「プレゼンをして褒められた」という体験を記憶に刻むことになるでしょう。
プレゼン自体を褒められた部下は「プレゼンを頑張れば評価してもらえる」と考えるようになる可能性があります。
本来、社内プレゼンは企画の承認や決済を取りつけるために行うのであって、プレゼン自体がゴールではありません。
社内向けの資料づくりに精を出し、仕事の目的を履き違えてしまう部下が育っていくリスクを孕んでいるのです。
承認欲求の否定にもとづく対応例
「次回もプレゼンで上司に褒めてもらいたい」という承認欲求は、専ら上司に対して向けられている点に問題があります。
特定の行為を上司の視点から捉えて褒めてしまうと、部下に誤った承認欲求を植え付ける原因になりがちです。
部下の行動やパフォーマンスを褒めるのであれば、次のように伝えるとよいでしょう。
- プレゼンのおかげで、企画がスムーズに通ったそうだ。
- 企画趣旨がよく分かったと、メンバーからも好評だよ。
上記はいずれも「第三者の影響力」を意識した褒め方です。
部下の仕事がチームや部門に貢献した事実を伝えることで、上司個人から認められたいという思いを根づかせないようにしています。
部下を褒めたり感謝の思いを伝えたりする場合には、横のつながりを意識して伝えることが大切です。
勇気づけを応用したマネジメントの例
アドラー心理学の柱の1つである「勇気づけ」は、マネジメントにおいても重要な概念といえます。
勇気づけは褒めることとどう違うのか、勇気づけにもとづく部下への対応例とともに見ていきましょう。
部下を「褒める」と「勇気づける」はどう違うのか?
「褒める」と「勇気づける」の決定的な違いは、相手に向ける視点にあります。
褒めるという行為は、相手が示した結果や成果を評価することに他なりません。
見方を変えると、褒められなかった結果については評価されていない、とも受け取れます。
一方、相手が今まで取り組んできたプロセスを肯定し、今後の取り組みを応援するのが「勇気づけ」です。
マラソン選手をゴール地点で待ち受けて「よくやった」と伝えるのが「褒める」ことと捉えてください。
勇気づけるには、ランナーの調子が良い時も悪い時も伴走し、横について励ます必要があるのです。
よくある誤った対応例
営業担当の部下から報告を受けた場面をイメージしてみましょう。
- 部下:今週は2件成約しました。
- 上司:2件も!素晴らしい。この調子で頑張ろう!
一見すると何の問題もないやり取りのように映るかもしれませんが、実は部下にとって2件の成約は「偶然降ってきた」ものに過ぎなかった可能性もあるのです。
たとえば、前任者が蒔いた種が実を結び、自分は運よく刈り取っただけだった、というケースもあるでしょう。
部下としては、次のような不満を抱く恐れがあります。
- 今回は大して何もしていないけれど、良い結果が出れば褒められるのか。
- プロセスがどうであれ、とにかく結果を出せばいいらしい。
- どんな手を使ってでも、結果を出すようにしよう。
結果として、他の担当者の手柄を横取りするなど、手段を選ばず成果を求める部下が現れるリスクがあります。
褒めればよいというものではなく、部下がどのような経緯で結果を出したのかを丁寧に聞き取っていくことが重要です。
勇気づけにもとづく対応例
部下を的確に勇気づけるには、必然的に進捗管理を行わなくてはなりません。
現状がどうであるのか、目標達成に向けたアクションをどのように計画しているのか、部下と一緒に考えていきましょう。
結果が出て初めて褒めるのではなく、途中経過で良いアクションが見られた際には肯定的なコメントをします。
反対に、進捗状況が思わしくない場合には、何がボトルネックになっているのかを突き止めておくことが大切です。
上司との協働を通して培った経験や知識は、将来的に部下が自走していくための糧となります。
的確な勇気づけには、きめ細かな進捗管理と状況把握が欠かせないのです。
まとめ
アドラー心理学は本来、マネジメントを想定した理論ではありません。
課題の分離・承認欲求の否定・勇気づけといったアドラー心理学の要素は、一般的な人間関係においても重視すべき概念といえます。
見方を変えると、マネジメントに求められるスキルや能力は人間関係を築く能力と通底しているともいえるのではないでしょうか。
マネジメント能力を伸ばしたいという思いが先走ってしまい、部下や従業員とじっくり向き合うことを忘れていませんか?
アドラー心理学への理解を深めることが、マネジメントの本質を改めて考えるヒントになるかもしれません。
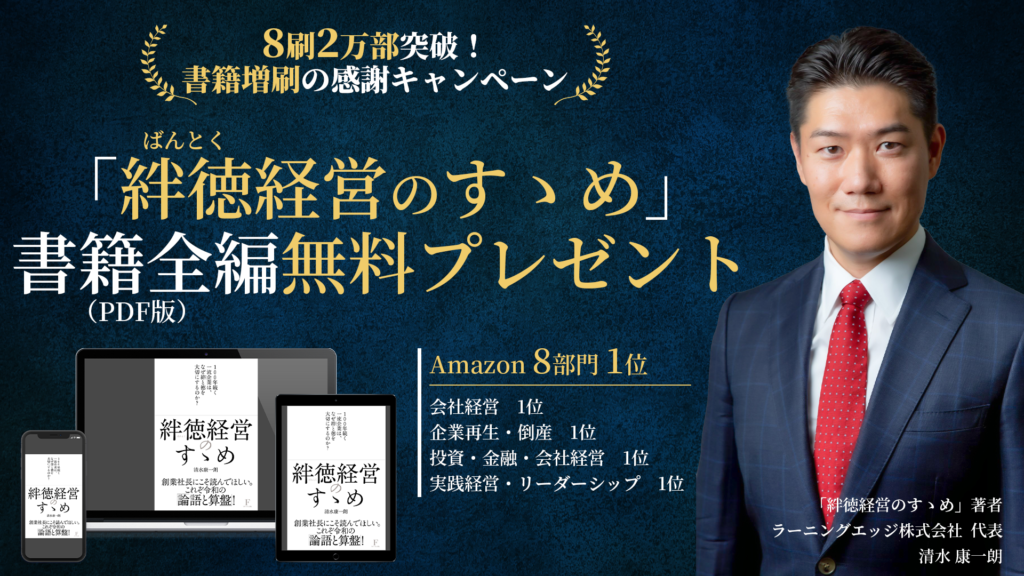
#アドラー心理学