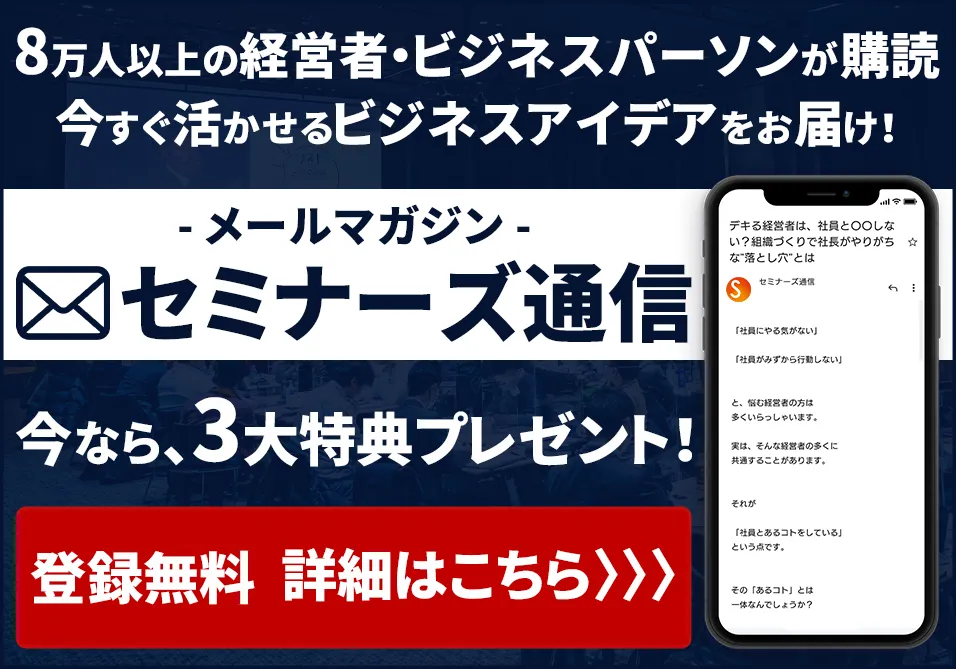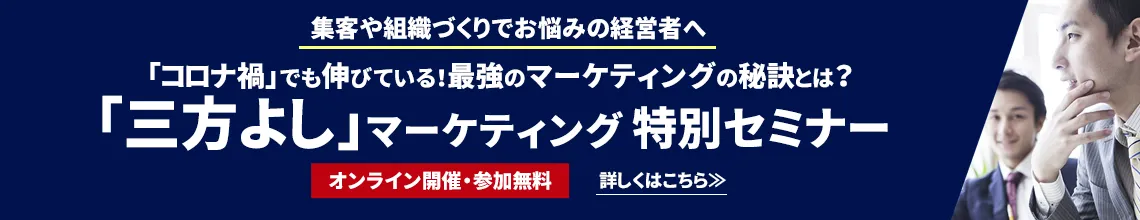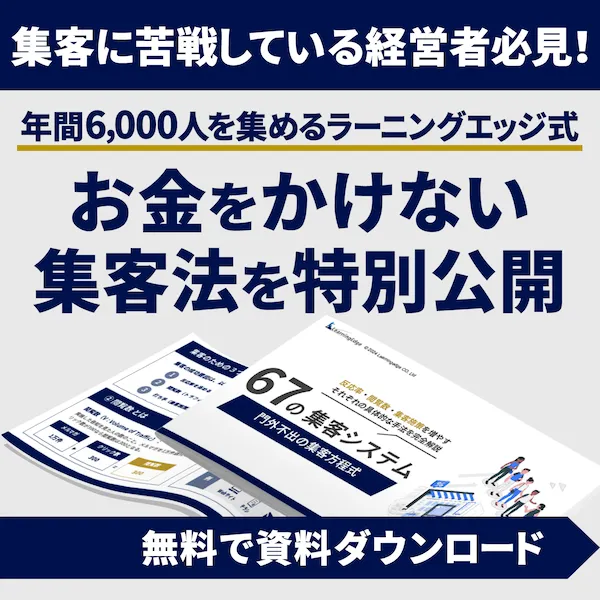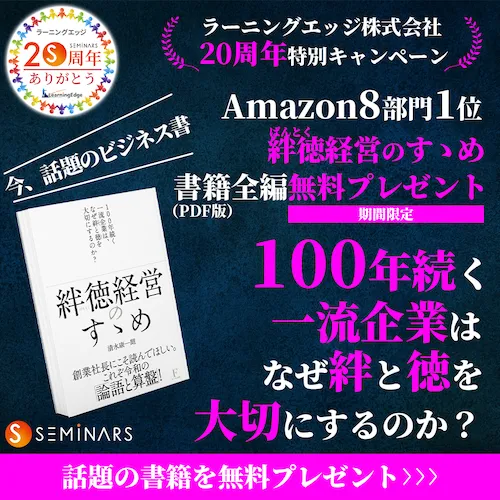社員のモチベーションをアップさせ自社の生産性を上げることは、どの企業においても必要なことです。しかし、自分の何気ない一言が部下のやる気を削いでしまったという経験がある人もいるのではないでしょうか。
社員のモチベーションを向上させるのに知っておくと良い心理効果に、ピグマリオン効果とゴーレム効果があります。
「ピグマリオン効果とゴーレム効果はどう違うのか」
「ピグマリオン効果を部下の教育に使いたい」
「なぜピグマリオン効果は人材育成に役立つのか」
このように考えている管理職や人事担当の方のために、この記事では以下の内容について説明します。
- ピグマリオン効果とゴーレム効果、その他の似た心理効果の特徴
- ピグマリオン効果を人材育成に生かすためのポイント
- ゴーレム効果を生まないためのポイント
ぜひこの記事を自社の社員のやる気を引き出す際の参考にしてください。
ピグマリオン効果とは

ピグマリオン効果とは、他の人から期待されることでパフォーマンスが向上し成果が出やすくなる心理効果です。教師期待効果やローゼンタール効果とも呼ばれます。
上司からプロジェクトを任せられた際に「あなたはきっとできる」と励まされたおかげで自信を持ち、プロジェクトで良い結果を出せたという状況はピグマリオン効果が働いたと言えます。
ピグマリオン効果の由来
ピグマリオン効果はギリシャ神話に登場する王様の名前に由来しています。ピグマリオンは腕の良い彫刻家でもありました。
ピグマリオンは自分で彫った女性の像に恋をしてしまい人間の女性になってほしいと願い続けたところ、女神アフロディーテがその願いを聞き入れ女性像に命を吹き込んだというストーリーです。
この神話から、期待をかけると良い結果になることをピグマリオン効果と言われるようになったとされています。
ピグマリオン効果の実験
ピグマリオン効果は、アメリカの心理学者であるロバート・ローゼンタールが実施した2種類の実験によって証明されています。
1つ目は1963年に行われたねずみの実験です。
個体差のないねずみを学生に与えた際、一方を「利口なねずみ」と伝え、もう一方を「利口でないねずみ」と伝えました。
「利口なねずみ」と伝えられた学生は、ねずみを丁寧に扱い「利口でないねずみ」と伝えられた学生は無意識にねずみをいいかげんに扱いました。その結果、個体差がないとされていたのにもかかわらず「利口なねずみ」の方が良い結果となりました。
学生のねずみに対する期待値が、ねずみの実験結果に反映されたと結論づけています。
1964年には小学生の成績に対する実験が行われています。
アメリカのある小学校の生徒に知能テストを受けさせました。その結果とは関係なく無作為に何人かの生徒を選び、担当教師に「今後成績が上がる生徒」というリストを渡したところ、リストの生徒は他の生徒よりも成績が良くなりました。
担当教師が「今後成績が上がる生徒」に期待をして指導し、それを生徒が感じ取ったことが成績アップに繋がったと考えられています。
どちらの実験でも期待をかけられたことが良い結果に繋がることを示しています。
ゴーレム効果とは

ゴーレム効果は、他の人から期待をされなかったり良い評価を得られなかったりすると、結果がどんどん悪くなってしまうという心理効果です。
ゴーレム効果には絶対的ゴーレム効果と相対的ゴーレム効果があります。絶対的ゴーレム効果は「あなたには期待していない」と言われたときに本当に成績が悪くなるような状態です。自己肯定感の低下などから生まれます。
相対的ゴーレム効果は周りが自分より能力の低い人ばかりの場合、自分の成績が下がってしまう状態です。周りの人とのレベルの違いが顕著で、自分だけが努力しても周りのレベルが上がらないためモチベーションの低下に繋がります。
ゴーレム効果の由来
ゴーレム効果のゴーレムとは、ユダヤ教の伝承に登場する泥人形のことです。ゴーレムは作った人の命令のみを聞くロボットのような存在で、ひたいに「emeth(真実)」と書かれた紙が貼られています。
「emeth」から「e」の文字を消すと「meth(死)」となり、ゴーレムは泥に戻り壊れてしまいます。
この物語から他人から受けた否定的な影響が自分の能力を失くしてしまうことをゴーレム効果と言うようになりました。
ゴーレム効果の実験
ゴーレム効果の実験もロバート・ローゼンタールによって行われています。
ある小学校で成績の良い生徒と成績の悪い生徒に分け、担任の先生に本当は成績の良い生徒を成績の悪い生徒と伝え、本当は成績の悪い生徒を成績の良い生徒だと伝えました。
担任の先生は本当は成績が良い生徒に期待しなくなり、本当に生徒の成績が悪くなってしまったという結果になりました。
もともと成績が良くても周囲に期待されなくなることで、悪い結果となってしまうことが証明されています。
ピグマリオン効果やゴーレム効果に似た心理効果

ピグマリオン効果やゴーレム効果に似た心理効果に、ホーソン効果とハロー効果があります。ここではそれぞれの特徴と違いを説明します。
1. ホーソン効果
ホーソン効果は、他人から注目されると期待に応えたいと感じて良い結果が生まれる心理効果です。
ホーソン効果はピグマリオン効果と似た心理効果です。ピグマリオン効果は他人の期待が結果に影響を与えますが、ホーソン効果は他人の注目や関心が結果に影響を与えます。
ホーソン効果はアメリカのウェスタン・エレクトリック社のホーソン工場で行われた実験で発見されたことから名づけられました。
2. ハロー効果
ハロー効果はその人の持つ1つの特徴によって、その人全体を評価してしまうという心理効果です。ハロー効果は1つの特徴で評価が良くなるポジティブハロー効果と、評価が悪くなるネガティブハロー効果の2種類があります。
ハローは光輪という意味で、太陽の周りに光輪が見えると太陽の形がわからなくなってしまうことから名づけられました。
ピグマリオン効果とゴーレム効果は他人からの期待が結果に影響を与えますが、ハロー効果はその人の一部が判断に影響を与えるという違いがあります。
ピグマリオン効果を人材育成に活かすための5つのポイント

ピグマリオン効果は企業の人材育成にも効果があります。上司が部下を育成する際のポイントを5つ紹介します。
- 期待を言葉にして伝える
- 適度な裁量権を与える
- 意見を聞く
- 期待しすぎない
- 褒めすぎない
ピグマリオン効果を最大限発揮できるような期待のかけ方・褒め方が重要です。
1. 期待を言葉にして伝える
上司が部下に期待していても言葉にして伝えなければ部下に伝わりません。「あなたに期待している」と言っても内容が具体的でなければ、部下に表面上の言葉だけと取られてしまうかもしれません。
具体的に褒めることで期待を知らせることが効果的です。仕事の成果だけでなくプロセスに着目したり、失敗の中でもできていることを評価したりすることで、部下は上司から期待されていると感じ取れます。
上司の期待を感じると、部下はモチベーションが向上し仕事のパフォーマンスが上がります。
2. 適度な裁量権を与える
部下は上司が事細かく指示してくると、自分は信頼されていない、自分は仕事ができないと思ってしまいます。上司はある程度の裁量権を部下に託し、部下の判断を信頼していると示すことが必要です。
部下はまだ経験が浅く半人前と感じるかもしれませんが、口出しせずに部下に任せることで信頼関係を構築できます。
裁量権が大きすぎると部下にとってプレッシャーとなるため、期間や予算を設定した範囲内や部下のレベルに合わせた裁量権を与えることで過度なプレッシャーを感じさせずに済みます。
部下が判断に迷う場合には、相談や質問がしやすい環境を整えておくことも重要です。
3. 部下の意見を積極的に聞く
ミーティングなどで部下にも意見を求めることで、部下に対して期待していることを示せます。
部下の意見を聞くときは下位の人から順番に発言してもらうのが、意見を引き出すためのコツです。先に上位の社員が発言してしまうと、下位の人は反対意見を出しづらくなるからです。
部下の経験や知識不足で意見を言えない場合は、質問に答えるなどのフォローも行います。部下が意見を言いやすいように日ごろからコミュニケーションをとっておくも大事です。
4. 期待しすぎない
上司が部下に期待しすぎると、期待がプレッシャーになってしまい成果に繋がらなくなってしまいます。上司の期待に報えないことから自信をなくすことにもなります。
過度な期待をしないためには、上司と部下で基準を決めることが大切です。仕事のクオリティや期限を明確にしておくことで、部下の能力以上に期待することを防げます。
部下が仕事に対してどう考えているのか、どのような将来像を描いているのかを把握せずに部下の理想と異なる期待を押し付けることも部下のモチベーションを下げてしまいます。
部下の能力やスキルだけでなく、仕事に対する意識なども理解して適度な期待をかけましょう。
5. 褒めすぎない
上司が部下を褒めることで期待を示せますが、褒めすぎてしまうと部下は現状に満足して向上心を抱かなくなる恐れがあります。上司が褒めたことを期待に応えられたと勘違いして手を抜くことも考えられるでしょう。
何でも褒めるのではなく、結果を出したプロセスに対して褒めることや部下の性格などを把握したうえで褒めることが大事です。
職場にゴーレム効果を生まないための5つのポイント

ゴーレム効果が生まれると職場全体の士気が下がり、生産性が低下します。上司の言葉一つでゴーレム効果が生じる可能性があるため、以下の5つのポイントに注意しましょう。
- 性格や能力を否定する発言をしない
- 失敗してもチャンスを与える
- 高すぎる目標を設定しない
- その場ですぐに褒める
- 減点方式でのフィードバックを減らす
ゴーレム効果があると自己肯定感が低下するため、成績が下がり成果が生まれなくなります。結果として部下の成長が阻害されてしまいます。
1. 性格や能力を否定する発言をしない
人の性格は変えることが難しいため、行動に焦点を当てて指摘することが重要です。性格を批判することは人格否定に繋がりやすく、パワハラやモラハラとみなされる可能性があります。
ミスをしてもその人の性格に問題があるわけではなく、間違った行動や外的要因がミスの原因となります。間違った行動をしていた場合は、その行動を改善するように指導しましょう。
2. 失敗してもチャンスを与える
部下が失敗した際には指摘して終わるのではなく、失敗を挽回するチャンスを与えることで部下に成長の機会を与えられます。
失敗は成功に必要な段階です。なぜ失敗をしたのかを考える場を提供することで、失敗をプラスに考えられるようになるでしょう。
人事の面でもマイナス評価で終わるのではなく、失敗から学び成功に結び付けられる場を部下に与えることでプラスの評価ができます。
3. 高すぎる目標を設定しない
ゴーレム効果は自己肯定感が低くなると陥りやすくなります。本人の能力に見合わない高すぎる目標を設定すると、目標を達成できずに自己肯定感が低下してしまいます。
上司は部下の実力を見極め、部下と話し合って成功体験を得られる目標を設定することが大事です。きちんと努力すれば目標を達成できると伝えることは部下に期待を示すことに繋がるため、ゴーレム効果が発生しづらくなります。
4. その場ですぐに褒める
部下を褒めることは部下のモチベーションを上げますが、時間がたってから褒めると効果は小さくなります。
タイミングが遅くなると今更感がぬぐえません。後から褒められても部下は何について褒められているのかわからなくなることもあるでしょう。
褒めるときは気づいたその場ですぐに褒めることが重要です。すぐに具体的な行動やプロセスを評価することで上司の思いが伝わりやすくなり、部下の記憶に残ります。
5. 減点方式でのフィードバックを減らす
改善点やミスの指摘をする減点方式のフィードバックは、部下のモチベーションを下げる恐れがあります。
部下がミスをしたときは減点方式のフィードバックが必要な場合もありますが、それだけでなく加点方式のフィードバックも合わせて行いましょう。
加点方式では部下が成功したことや改善できたことに視点を置くため、ゴーレム効果でなくピグマリオン効果が生まれやすいです。部下の悪い面を見るのではなく、良い面に目を向けることで期待を示せます。
伝え方でピグマリオン効果とゴーレム効果のどちらが起こるか決まる
この記事では、ピグマリオン効果とゴーレム効果の特徴や上司が注意すべきポイントなどについて説明しました。
ピグマリオン効果とゴーレム効果は真逆の結果を生む心理効果です。上司が部下にどのような言葉を伝えるかで、どちらの効果が発生しやすくなるかが決まります。
普段から上司が部下に対して期待していると言葉にして、部下が仕事に対して自信を持たせることが重要です。上司の背中を見せて学ばせるのではなく、言葉で伝えることで信頼関係が構築できます。
上司の方は自分の言動がピグマリオン効果に繋がっているか、ぜひ意識してみてください。
年商5億円を超えさらなるスケールアップを目指す経営者必見!
あなたのビジネスをスケールアップさせる集客と組織作り、
さらに、成功事例やここだけのお得な内容をお届け致します。