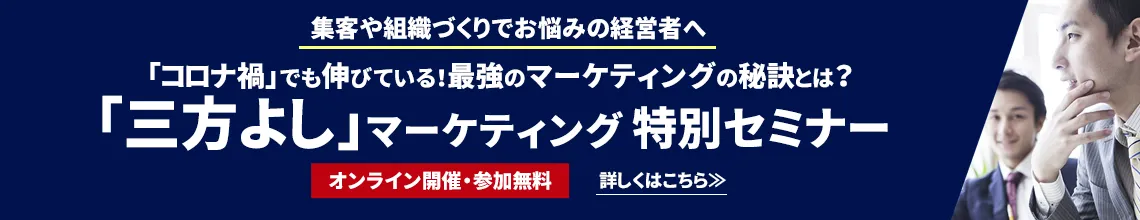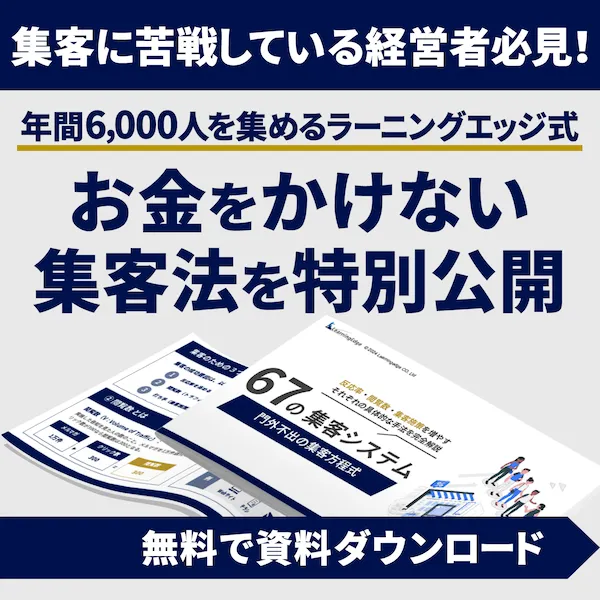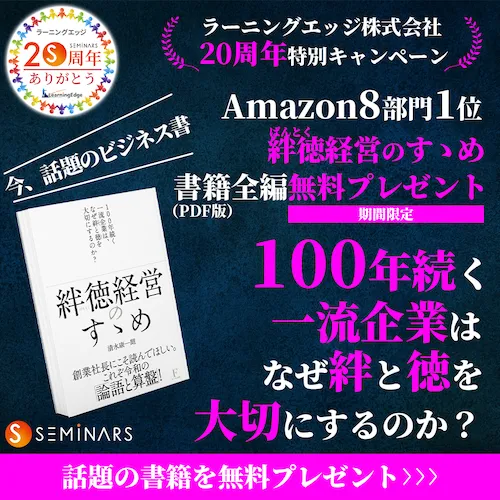かつて近江商人が経営理念として掲げていた「三方よし」の精神を取り入れる企業が増えています。
古くからある考え方なので、「もう古いのでは?」「取り入れるメリットはある?」と疑問を感じる人もいるでしょう。
そこで今回は三方よしの精神とはどんなものなのか、経営に取り入れる方法などを詳しく解説します。
現代の世の中だからこそ注目される三方よしの精神を知り、経営に反映させていきましょう。
三方よしの「三方」とは
三方よしの「三方」とは、「売り手」「買い手」「世間」の三方にとってプラスになる状態を目指すための経営理念です。
売り手や買い手だけでなく、世間が良くなる経営で社会貢献を行うことによって、事業の末永い継続を目指しています。
では三方それぞれの詳しい意味を解説していきましょう。
売り手
「売り手」は商品やサービスを提供する企業を指します。
売り手となる企業がコストに見合う利益を出している状態が「売り手よし」です。
根本的に、売り手が利益を出さなければ事業を存続できません。
買い手や世間にリソースを割きすぎていると、「売り手よし」の状態を保つことが難しくなります。
たとえば、商品やサービスの価格が質に見合っていないと利益につなげることができません。
市場調査や競合調査をきちんと行い、適正価格で商品やサービスを提供しましょう。
また、買い手である顧客のサポートに時間を割きすぎると、人材を無駄に消費することにもつながります。
顧客満足度は企業の存続にとって重要な項目ですが、リソースとメリットのバランスを意識して「買い手」に偏らないように気をつけてください。
買い手
「買い手」は自社の商品やサービスを購入する顧客を指します。
顧客満足度が高い状態が「買い手よし」です。
しかし、気をつけなければいけないのが、すべての顧客が満足する状態を作り出すことが「買い手よし」につながるわけではないという点です。
顧客にはそれぞれニーズがあります。
たとえば、一つの商品を購入するときに価格に重きを置く顧客もいれば、商品の機能や質に重きを置く顧客もいるでしょう。
この両極端なニーズをすべて満たそうとすると、誰にとっても魅力のない商品やサービスになってしまうことも少なくありません。
そのため、きちんとターゲットを絞り込み、ターゲット層の顧客が満足できる商品やサービスを提供しましょう。
また、ターゲットに合わせたマーケティングも、顧客満足度を高めるために重要です。
世間
「世間」は、売り手と買い手以外の第三者や、社会を指します。
世間に貢献して自社の良いイメージをキープできている状態が「世間よし」です。
どんなに顧客満足度の高い商品やサービスを提供し、企業として利益をあげていても、世間の評判が悪い企業は存続を危ぶまれます。
たとえば、商品を製造するために環境汚染を行っている企業は、「世間よし」とはいえません。
また、従業員の満足度が低い企業も「世間よし」を実現しているとはいえないでしょう。
残業や過酷な業務を強いるなど、従業員の働く環境が悪いと、商品やサービスの品質低下にもつながります。
優秀な人材の流出は企業としても大きな損失です。
「世間よし」を目指すことは、結果的に売り手や買い手の満足につながるといえるでしょう。
三方よしとは?売り手良し、買い手良し、世間良しの事業事例を紹介
「三方よし」とは近江商人がもとになった考え方
「三方よし」は、現在の滋賀県にあたる近江の商人がもとになった考え方といわれています。
江戸時代、近江を中心にほかの地域に向けて商いを行っていた近江商人は、取引先の土地柄や社会情勢を踏まえて活動していました。
自分たちの地域から離れても、売り手や買い手だけでなく、取引先の地域にも愛される商品や企業を目指したのです。
三方の満足度を重視した考え方は、当時「売り手」と「買い手」の満足度を重視していた商人と差をつけ、「楽市楽座」を発展させたといわれています。
近江商人のビジネス哲学
近江商人のビジネス哲学の核心には「三方よし」の精神があります。
これは売り手、買い手、そして社会全体が満足する取引を目指すというもの。
近江商人の歴史とその商売の特徴、そして現代ビジネスにどのように適用できるかを見ていきましょう。
近江商人の歴史とその商売の特徴
近江商人は、主に滋賀県近江地方に起源を持つ商人で、江戸時代から活躍していました。
近江商人の商売の特徴は、顧客との長期的な関係を大切にし、信頼と誠実を基本に置いた取引をするところ。
一時的な利益を追求するのではなく、持続可能なビジネスを築くことに注力したのです。その結果、顧客との強固な信頼関係が築け、地域社会へも深く貢献することができました。
「持続可能なビジネス」という哲学は、まさに現在で求められている価値観です。
近江商人に学ぶビジネスモデルと経営戦略
近江商人のビジネスモデルは、現代のビジネスにも応用が可能です。
「三方よし」の精神は、持続可能なビジネスの原則。現代でも多くの企業で採用されています。
①顧客中心のビジネス
近江商人は顧客のニーズを最優先に考え、顧客満足を追求してきました。
これは、顧客体験と顧客満足の向上が重要であるという現代ビジネスの原則と一致しています。
②持続可能な経営
一時的な利益よりも、長期的な信頼と関係を重視する経営は、持続可能なビジネスモデルの構築に不可欠です。
環境、社会、ガバナンス(ESG)の観点からも、この哲学は現代ビジネスにおいて押さえておきたいポイントの一つです。
③社会貢献
近江商人は、「ビジネスは地域社会に貢献するものであるべき」という意識を持っていました。
これは、企業の社会的責任(CSR)として、ビジネスの社会的価値が求められる現代の背景と重なります。
---
このように、近江商人のビジネス哲学からは多くのことが学べます。
それは単に歴史的な教訓ではありません。現代ビジネスの成功と持続可能性に直結した、普遍的な原則を学ぶことができるのです。
これらの原則を現代ビジネスに取り入れることで、企業は持続的な成長と社会的価値の創造を実現できるでしょう。
「三方よし」の考え方はもう古いのか
「三方よし」の考え方が生まれたのは江戸時代といわれているため、「古い考え方」と思う人もいるかもしれません。
しかし、「三方よし」の精神は経営の根本となる考え方なので、現在も「三方よし」を経営理念に掲げる企業も多くあります。
売り手と買い手だけでなく、世間の三方が満足する商売は理想論と考える人もいるでしょう。
とくに顧客と世間が満足するためには、ある程度のコストがかかるため、売り手の利益が減ってしまうと考えるのが一般的だからです。
しかし、時代の変化とともに商品=物という認識は薄まりつつあります。
たとえばネットフリックスなどの動画配信サービスは、コストを最小限に抑えて利益を最大化した例といえるでしょう。
このように、目に見える商品ではなく、価値を提供するサブスクリプション型のサービスは年々増加傾向にあります。
消費したコスト=顧客満足度につながるわけではありません。
最小限のコストで「三方よし」を目指すことで、継続的に利益をあげることができるでしょう。
三方よしと現代ビジネス
近江商人の「三方よし」の精神は、現代ビジネスにこそ活かしていきたい価値観です。
特に、企業の社会的責任(CSR)との関連性です。しかし、「三方よし」と「CSR」では異なる部分も存在します。
それぞれの違いを見ていきましょう。
CSRと三方よしの関連性と違い
■ 関連性:
CSRと三方よしは、両者ともに
- 企業は利益を追求するだけではない
- 社会に対しても責任を果たす必要がある
という基本的な価値観に基づいています。
これは、企業が持続可能な成長を達成するためには、顧客、従業員、地域社会、環境など、多様なステークホルダーとの調和が必要という考え方です。
■ 違い:
一方で、CSRは主に企業の社会的、環境的責任に焦点を当てたものであり、具体的なアクションや指標が求められます。
それに対して、三方よしは、商取引において売り手、買い手、そして社会全体が満足するという、よりシンプルで根本的な原則に基づいています。
三方よしを経営に取り入れる方法
三方よしを経営に取り入れる方法は次の3ステップです。
- ステップ1:分析を入念に行う
- ステップ2:ターゲットを明確にする
- ステップ3:顧客の問題を解決に導く商品やサービスを提供する
この3ステップを踏むことで、「売り手」「買い手」「世間」の満足につながるでしょう。
分析を入念に行う
三方よしを目指すためには、分析を入念に行ったうえで企業理念を決めるのが大切です。
まずは自社が属する業界の市場調査を行い、業界のニーズやトレンドを把握しましょう。
あわせて明確にしておきたいのが自社の強みです。
業界のニーズや課題に対して、自社ができることは何かを明確にし、買い手の満足する商品やサービスの開発につなげましょう。
反対に企業として行いたくないことや避けるべきことを、はっきりしておくのも大切です。
自社の目指すイメージが明確になれば、「世間よし」を実現するために何をすべきか、おのずと見えてくるでしょう。
ターゲットを明確にする
分析を入念に行い、企業理念を明確にしたら、ターゲットを決定しましょう。
自社ができることや強みをもとに、どの年齢層や客層にアプローチするのが最適かを明確にします。
このとき、顧客のパーソナリティだけでなく、どんなニーズやウォンツを抱えているのかを深堀りすることが大切です。
ただしカスタマーファーストになりすぎると「買い手よし」に偏ってしまいます。
自社のリソースのなかで解決できる顧客の課題や問題はなにかを的確に分析するのが、「三方よし」を目指すコツです。
顧客の問題を解決に導く商品やサービスを提供する
ターゲットの課題や問題を把握したら、解決に導く商品やサービスを開発します。
顧客が悩みや問題を解決できると判断しないと、商品やサービスの購入につながりません。
適切なマーケティング活動を行うためにも、4C分析などのフレームワークで顧客が購入に至るまでの要素を分析するのがおすすめです。
4C分析は次の4つの項目で構成されています。
- Customer Value(顧客価値)
- Cost(顧客のコスト)
- Convenience(顧客にとっての利便性)
- Communication(顧客とのコミュニケーション)
顧客の購買心理や行動を正確に把握してマーケティング活動を行うことで、売り手の利益にもつながります。
マーケティングに役立つフレームワークを詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてみてください。
三方よしの精神を経営に取り入れて成功した企業
三方よしの精神を経営に取り入れて成功した企業の事例を3つ紹介します。
- 伊藤忠商事
- 株式会社高島屋
- ラーニングエッジ
それぞれ独自の方法で「三方よし」を取り入れているので、ビジネスモデルとして参考にしてみてください。
伊藤忠商事
引用元:伊藤忠商事
大手総合商社である伊藤忠商事は、近江商人である伊藤忠兵衛氏が創立しました。
関西から関東に向けて商いを行っていた伊藤忠兵衛氏は、「三方よし」の考えをもとにその土地や風習に合った商売方法を模索して成功を収めた人物の一人。
2022年現在、機械やエネルギー分野をはじめ、金融、繊維、食料など、さまざまな分野に進出する大きな会社に成長しています。
またSDGsにも積極的に取り組んでおり、グループ全体でサスティナビリティを推進しているなど、売り手や買い手だけでなく、常に社会貢献を意識した活動を行っているのです。
株式会社高島屋
引用元:株式会社高島屋
株式会社高島屋の創業者である飯田新七氏は、「三方よし」の精神をもとに会社を大きく成長させたといわれています。
飯田新七氏は近江商人の婿養子であったため、「三方よし」の考え方が身近にある環境で生活していました。
そのため、自然に経営にも三方よしの考えが反映されたといえるでしょう。
百貨店としてさまざまな商品を扱う高島屋は、2022年現在もサスティナビリティの推進に力を入れています。
食品ロスの改善や衣料品の回収を行うなど、日々SDGsを達成するために活動しているのです。
また、従業員に向けても「能力開発制度」を設けて、売り手よしの状態を目指しています。
ラーニングエッジ株式会社

引用元:ラーニングエッジ
ラーニングエッジは「全従業員の物心両面の豊かさを追求すると共に教育を通じた社会の成長発展に貢献します」という経営理念のもと、経営者向けのビジネスセミナーの企画・運営やビジネススクールの運営を行っています。
買い手が満足するよう、質の高いサービスを提供するのはもちろん、「売り手よし」を実現するために従業員の教育環境の整備や、適切な評価制度を導入しています。
また、売上の一部を寄付やボランティア活動に充てるなど、「世間よし」についても積極的に取り組んでいます。
従業員のスキルやモチベーションアップは会社の生産性向上につながり、上がった売上で社会貢献に取り組むことで、売り手である会社も成長を遂げているのです。
「三方よし」を取り入れて成功した企業について、さらに詳しい事例を知りたい人は、こちらの記事も参考にしてみてください。
三方よしとSDGsの関連性とは
2030年までに達成すべき持続可能な開発目標として制定されたのが「SDGs」です。
項目数は17と多岐に渡りますが、本質は「三方よし」と共通しています。
というのも、SDGsは貧困や格差などの経済環境や気候変動などの外的環境に関わる問題を解決し、すべての人が住みやすい世の中をつくることが目的。
「売り手」「買い手」「世間」の3つの要素が含まれていることから、「三方よし」が目指す状態と通ずるものがあるといえるでしょう。
新型コロナウイルスの影響を受け、世界全体が大きな方向転換を迫られている状態です。
アマゾンやアップルなど、アメリカのトップ200の主要企業が会員となっている経済団体ビジネス・ラウンドテーブルは、企業や顧客、従業員、株主、取引先、金融機関など、すべてのステークホルダーに貢献すると表明しています。
売り手と買い手だけを重視したマーケットインやプロダクトアウトに偏った考え方ではなく、社会を含めた「三方よし」の考え方に世界が注目しているのです。
よくある質問
Q1: 三方よしの原則は、具体的にどのようなビジネスシーンで活かされていますか?
三方よしの原則は、
- 企業倫理の強化
- 顧客満足度の最大化
- 社会貢献活動の推進
などのビジネスシーンで活かされています。
これは
・顧客との長期的な関係構築
・持続可能なビジネスモデルの確立
などに効果的です。
Q2: 近江商人のビジネス哲学を小規模ビジネスやスタートアップにどのように適用すれば良いですか?
小規模ビジネスやスタートアップでも、近江商人のビジネス哲学を応用することができます。
近江商人の「三方よし」は、売り手・買い手・社会全体が満足する取引を目指すというもの。
小規模ビジネスやスタートアップであっても、利益の創出だけに走らず
- 顧客との信頼関係を深化させ
- 持続的な価値を提供するビジネスモデルを構築する
ことに意識を置くことで、「三方よし」の哲学を効果的に適用できます。
Q3: 三方よしの精神を組織文化として浸透させるための方法は?
三方よしの精神を組織文化として浸透させるためには、経営層が率先してこの価値観を共有し、それを組織全体に広めることが重要です。
- 定期的な教育とトレーニング
- 実践を通じたフィードバックと改善
- 三方よしの精神を日々の業務に組み込む
以上のステップを踏んで、組織文化として根付かせていきましょう。
まとめ
「三方よし」は江戸時代に活躍した近江商人が、ほかの地域でのビジネスを拡大するために培った考え方です。
しかし、現代でも「三方よし」を経営理念に掲げて成功している企業はたくさんあります。
月日が流れ、さまざまなテクノロジーが生まれても活用できる普遍的な考え方、それが「三方よし」なのです。
世界共通の開発目標であるSDGsを実現するためにも、「三方よし」の考え方は今後も大切になってくるといえるでしょう。
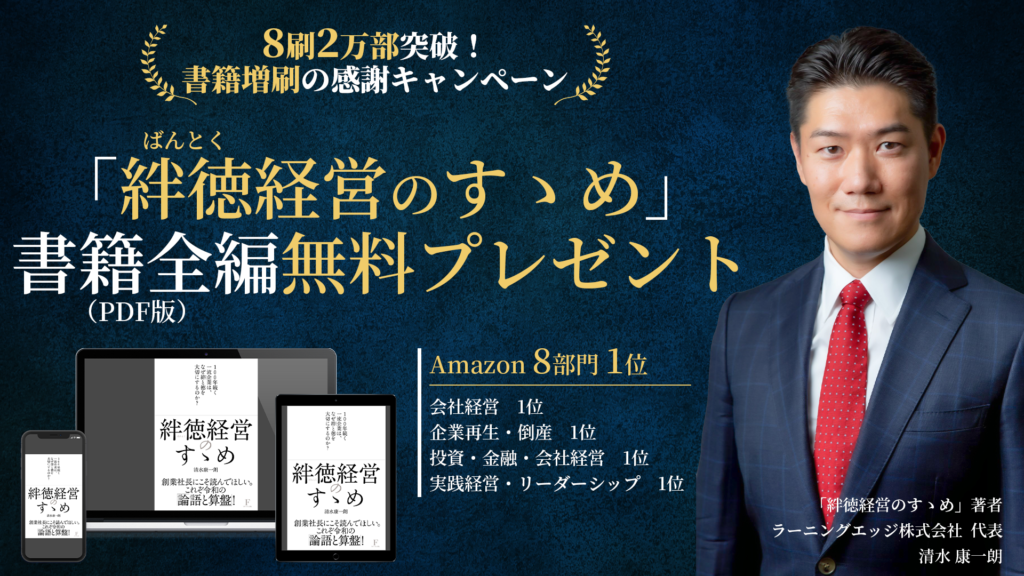
#三方よし #ビジネススクール #三方よし企業 #経営スクール